皆さん、こんにちは。
哲学倫理・心理・歴史、それから本紹介の記事を書いています、よっとんです。
本日は、恐らく日本で女性への差別を無くすことを主張した初めての人物である森有礼をお届けします。
森有礼は明六社という団体の出版物『明六雑誌』の中で男女平等について書いています。
「森有礼って誰?」という人にもわかるように書きましたので、
気軽にご覧くださいませ!!
そもそも明六社って何?

明六雑誌 第十号 1874年(明治7年)6月 明六社発行 <表紙>https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Meiroku_Zasshi_No10_1874_Cover.jpgより引用
明六社は明治六年(1873)にできた、学術団体です。
何を学としていたかというと、「啓蒙思想」です。
「啓蒙思想」とは日本の場合は、蒙昧(無知)を啓く(ひらく)という意味で、
簡単にいえば、「凝り固まった考えを、解きほぐそう」とする思想です。
※西洋では「光を当てる」という意味で、理性で迷信や非合理的な考えを排除しようという考えが基にあります。
そして、明六社を創設した人物こそ、森有礼です。
なぜ創設したのか・・・それは、彼の英米留学がきっかけでした。
彼は戊辰戦争前後に英米に留学(密航でしたが…(笑))に行っていました。
そこで、日本との差を見せつけられました。
鉄道・蒸気船・エレベーター・織物機などなど…
森有礼はこの発展を可能にしているのは、
実証主義に基づいた科学、哲学的な思考、そして知的な風土があるからに違いないと考えました。
「根本的な考え方から全く異なる・・・日本を教育しなおさなければ・・」と痛感します。
そして、そのためにも
「日本にも欧米のような学術団体が必要だ!」
そこで、彼は日本を代表する学者に呼び掛けて明六社を創設したのでした。
メンバーは西村茂樹,津田真道,西周,中村正直,加藤弘之,福沢諭吉,箕作秋坪,神田孝平ら
超有名人になります。
「福沢諭吉!他は・・・えっ?誰??」・・・と言う方もいると思います。
違う記事にて説明しますので、記事が上がりましたら、そちらも参考ください!
次に、森有礼の思想を見ていきましょう。
森有礼:男女は平等だ!(妻妾論)

森有礼は薩摩出身でした。
同じ薩摩藩の五代友厚らとともにロンドンへ留学(密航)し、
その後、ローレンス・オリファント(英人作家)の誘いでアメリカへ留学、
帰国後、明六社を設立したというのは先ほど述べた通りです。
ただ、彼の一躍有名にしたのは、明六社時代ではなく、
1885年になります。
なんと彼は、初代の文部大臣なのです。
彼の発布した「学校令」で、初等部・中等部・高等部ができあがりました。
ということは、今の教育システムの基礎を作りあげた人でもあるのですね…
そんな彼が、明六社時代に明六雑誌に残したのが「妻妾論」です。
「妻妾論」には革新的なことが書いていました。
例えば、
- 男女は平等であること
- 男は女性を扶助する義務があること
- 妻は夫から扶養される権利と夫を扶助する権利があること
などです。
「えっ?革新的なの?」
と思われるかもしれませんが、男女平等や扶助・扶養と江戸時代までの日本にはありませんでした。
親同士が決めた者との結婚が普通でしたし、妻以外に妾(側近)を持っても非難されませんでした。
有礼はその妾を囲う習慣を非難し、
夫婦の相互的な権利と義務に基づく、一夫一婦制の婚姻形態を提唱しました。
有礼は、夫婦が互いに男女を平等に扱うようになることから国の基礎ができてくると考えていたのです。
そんな彼は自分自身で一夫一婦制をアピールしていきました。
今は普通ですが、森有礼は「契約結婚」を日本で初めてした人物です。
相手は幕臣広瀬秀雄の娘の広瀬常さんでした。
※後に契約に沿って離婚もするのですが…
それから、現代に近い結婚式も行いました。
多くの招待者が見守る中・・・ドレス・スーツの洋装の男女が腕を組み、歩いてくる・・・
「なんだこれは?」
当時の人々はこんな反応だったのではないでしょうか。
この結婚のありかたには皆が驚き、新聞記者までかけつけたそうです。
形式に沿って、婚姻誓約書が読まれ、署名。
その時の証人はなんと明六社のメンバーの一人である
福沢諭吉でした。
有礼は以前、福沢諭吉に
「明六社のトップになってほしい」
と頼むほど、福沢諭吉のことを信頼していました。※拒否されたんですけどね(笑)
また、福沢は女性の権利や男女の平等を論じていたことでも有名ですね。
実際に、アメリカへ行って女性と写真を撮ったりしています。
※女性と二人で写真を撮ること自体、当時では新しいことなので!
だから、有礼が福沢諭吉を証人として呼んだのも納得ですね。
契約結婚と結婚式、こうして名実ともに一夫一婦制を体現したのでした。
ただ、彼は文部大臣時代に「良妻賢母教育が国是だ」
という主張もしています。
これは、今の考えでは差別的だと思われるかもしれませんが、
当時はどうもそういう意図はなかったようです。
明治になると、江戸期のように「家」で働くのではなく、
徐々に労働者として働きに行くということが増えてきました。
従来なら、女性も「家」で職業的な役割があったのですが、
工場での労働や出稼ぎを男性がやるようになり、「家」のシステムが崩壊していくにつれて、
女性の役割がいわゆる「主婦」になっていきました。
そこで政府が打ち出したのが、「良妻賢母教育」でした。
有礼は「妻妾論」の中でも「夫は妻を扶養する義務がある」と主張していただけなので、
「良妻賢母」を説いたとしても、彼の主張自体に矛盾があったわけではないと思います。
もちろん、「主婦=女性」であること自体は今の感覚でいえば間違ったものですが、
当時はその感覚自体がない人の方が多く、
結果的に「男性は外へ、女性は家で役割を担う」という形が「普通」になっていきました。
※この形態自体が「普通」になっていることに疑問をもった人もいました。有名なのは平塚らいてうです。詳しくは以下を参照ください。
『女性差別はどう作られてきたか (集英社新書) 中村 敏子』
さて、有礼の最後をお話しして、締めくくりましょう。
有礼は最後はとても残念なものでした。
1889年、彼は大日本帝国憲法発布の式典に参加しようとしていました。
「よし、いくぞ」
官邸を出たとたん、
ぐさり・・・
国粋主義者が持っていた短刀で刺されてしまったのです。
病院へいくも、傷が深く、その後死亡してしまいました・・・。
なぜ国粋主義者が恨みをもっていたのか理由は定かではないのですが、
Wikipediaさんによれば、
「大臣の誰かが、伊勢神宮の拝殿に土足であがった」という記事が新聞が報じられ、実際犯人は確定していませんでしたが、「その犯人は森有礼なのでは」と疑われていました。それが原因で刺されたらしいです。
とても悲しいですね。
まとめ
森有礼について、いかがだったでしょうか?
彼が明六社を設立したこと、
そして「男女平等」を説き、自分自身で一夫一婦制を体現してみせたこと、
この事実はとても意味あるものだと思います。
ここまでご覧いただき、本当にありがとうございました。
他にも多数記事がございますので、よろしければぜひご覧ください。
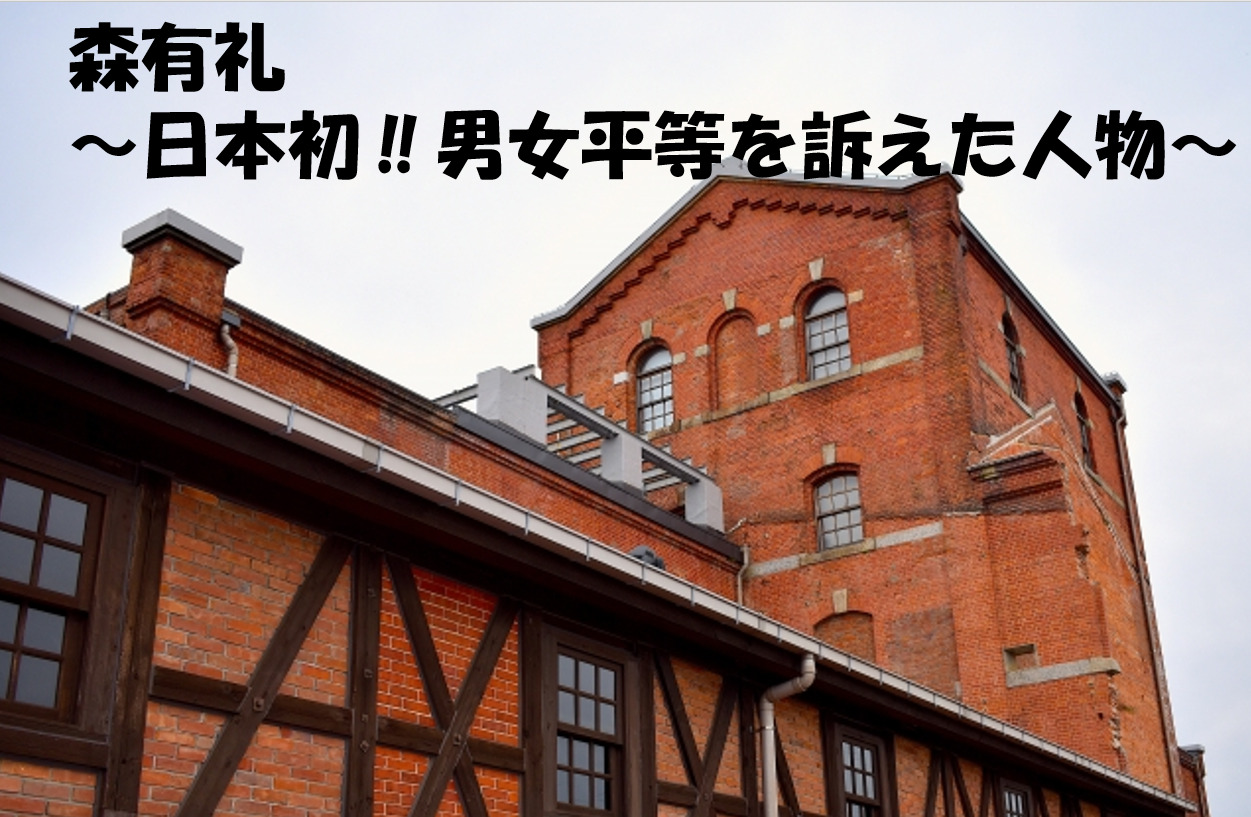



コメント