こんにちは。
本日は地理総合の分野で扱われている「GIS(地理情報システム)」について書いていきたいと思います!
- そもそもGISっていうのは何なのか?
- GISってどんな仕組みなのか?
- GISで何ができるのか?
について述べていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください!
GIS(地理情報システム)とは?

GISは「地理情報システム」の略で、地理に関する情報を取得し、管理するシステムのことです。
難しく聞こえるかもしれませんが、実は私たちの身の回りにある地図サービスの多くがGISを活用しています。
たとえば、普段使っているGoogleマップや、国土地理院が提供する地理院地図などもGISの一種です。
これらの地図は、実は複数の「地理情報」(これをレイヤーと呼びます)を重ね合わせて作られています。
レイヤーとは?
レイヤーとは、特定の種類の地理情報だけをまとめたものです。例えば、以下のような情報がそれぞれ別のレイヤーとして扱われます。
- 路線のレイヤー: 電車やバスの路線情報
- 土地利用のレイヤー: 商業地、住宅地、森林などの土地の使われ方
- 区市町村のレイヤー: 行政区画の情報
- 公共施設のレイヤー: 学校、病院、図書館などの位置情報
GISの仕組み
GISでは、これらの個別のレイヤー(地理情報)を収集し、それぞれ別々に管理します。
そして、必要に応じてこれらのレイヤーを重ね合わせる(これをオーバーレイと呼びます)ことで、私たちが目にしている地図が作られるのです。
つまり、GISは一つ一つの地理情報を集め、管理し、さらにそれらを組み合わせて多様な地図として表現する、そのすべてを担うシステムだと言えます。
「GIS」という言葉は聞き慣れないかもしれませんが、実は身の回りにある便利な地図サービスは、すべてこのGISのおかげで成り立っています。
地理情報の集め方:現代の方法
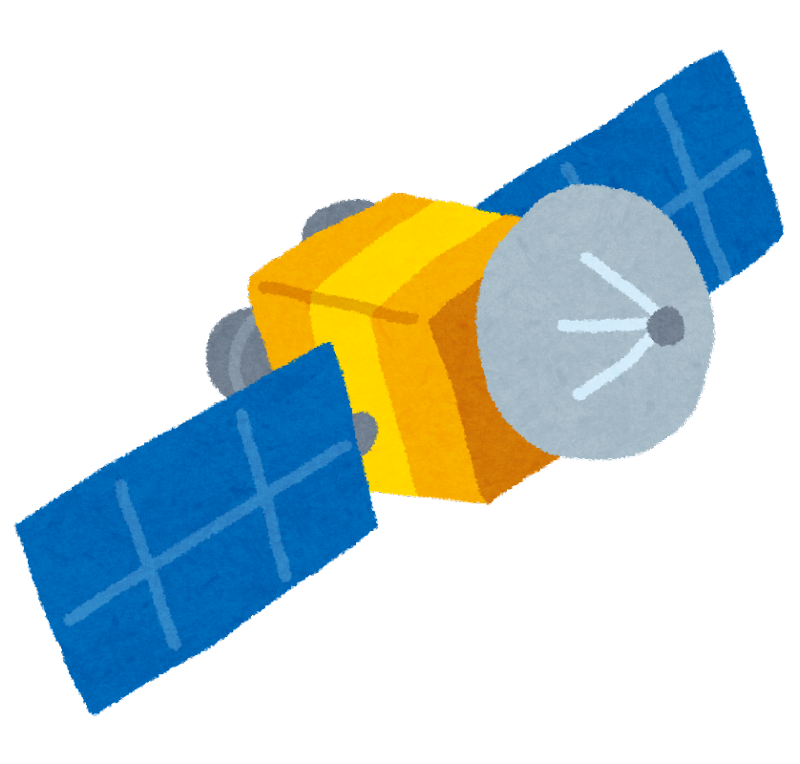
昔は、新しいお店の場所を調べるのに、実際にその地点まで出向くこともあったかもしれませんね。
まるで伊能忠敬のように、足を使って地図を作っていた時代もありました。
しかし、現代ではそんな手間のかかる方法はもう必要ありません!
今の地理情報の取得には、主に衛星や飛行機が使われます。
このように、離れた場所から情報を調査・取得する方法を「リモートセンシング」と呼びます。
具体的には、人工衛星が地球上の情報をキャッチし、その情報を緯度と経度に合わせて地図上に表示することで、私たちが普段目にしている地理情報が作られています。
昔に比べて、地理情報の収集は格段に簡単で効率的になりましたね!
GISの種類と便利な活用例

GISには大きく分けて2つのタイプがあります。
- WebGIS: インストール不要で、ウェブブラウザからアクセスして利用するタイプです。
- デスクトップGIS: パソコンにソフトウェアをインストールして使うタイプです。
どちらのタイプも、さまざまな地理情報を扱うことができます。
GISの活用例
身近なGISの例としては、以下のような便利なサービスがあります。
- 国土地理院地図 このWebGISでは、地図上の「距離」や「面積」を測ったり、「断面図」を作成したりできます。さらに、「年代別の空中写真」を見たり、「洪水や地震の際の避難場所」を検索したりすることも可能です。 国土地理院地図
- 今昔マップon the web これは、昔の地図と現在の地図を比較できる非常に便利なWebGISです。地域の歴史的な変化を知るのに役立ちます。 今昔マップon the web
このように、GISは多様な地理情報を収集し、管理しているため、かつては地形図を使って手作業で行っていた「縮尺を考慮した距離測定」や「標高からの断面図作成」といった作業が不要になりました。
インターネット環境があれば、現地に行かなくても瞬時に距離や断面図を確認できるため、将来的には紙の地形図が使われなくなるかもしれません。
GISは普及した理由とは?
日本におけるGISの普及は、実は世界的に見ても遅れていました。
その背景には、地理情報が過去に戦争で利用されてきた経緯があります。
戦時中は陸軍が地理情報を厳重に管理していたため、一般の人々が自由にアクセスすることはできませんでした。
しかし、ある大きな出来事をきっかけに、この状況は大きく変わることになります。
それが1995年の阪神・淡路大震災でした。
この震災では、GISが整備されていた地域とそうでない地域とで、避難できた人数の差が顕著に現れたのです。
この事態を重く見た政府は、地理情報をよりオープンにし、広く活用していく方針へと転換しました。
そして、その流れを受けて2007年には「地理空間情報活用推進基本法」が制定されました。
この法律を機に、日本でも地理情報の整備と活用が本格的に進められるようになったのです。
まだ10年程度の歴史であり、GISという言葉自体は十分に浸透しているとは言えないかもしれません。
しかし、今後GISは私たちの生活にますます深く関わり、やがては誰もが当たり前のように使う言葉になることでしょう。
私たちの身近なGPSもGISの仲間!

最後に、GPSについてです
私たちが普段使っているGPSも、実はGISの技術を活かしたシステムの一つです。
厳密に言うと、GPSは「GNSS(全球測位衛星システム)」という、人工衛星を使って位置を特定するシステムのアメリカ版の名前です。
GNSSには、アメリカのGPSの他にも、日本の「みちびき」やEUの「ガリレオ」など、様々な種類があります。
しかし、GPSという言葉が広く浸透しているため、GNSS全体を指す言葉として「GPS」が使われることが多いのが現状です。
例えるなら、電子決済の一種である「Suica」が、他の電子決済も含めて「Suicaで!」と言われるような感覚ですね。
GPS(GNSS)の仕組み
GNSSもまた、人工衛星を使って情報を取得しています。
宇宙にある人工衛星が、私たちのスマートフォンなどから発せられる電波を受信し、その距離を特定します。
人工衛星が1台だけでは、距離はわかっても正確な位置はわかりません。
そこで、3つ以上の人工衛星が同時に距離を測ることで、それぞれの距離が交わる1つの点を特定し、正確な位置を割り出すことができます。
日本の「みちびき」が拓く未来
現在のGPSでは、位置の誤差が数十メートルほどあると言われています。
しかし、日本の「みちびき」は、2023年に7機体制となることで、その誤差がなんと数センチメートルにまで縮まりました。
これまでの技術では、私たちが「自分の部屋にいる」ことは特定できても、「部屋の中の机にいるのか、それともベッドで寝転んでいるのか」まではわかりませんでした。
しかし、「みちびき」が7機体制になれば、もしかしたらあなたが勉強をサボってベッドにいることまでバレてしまうかもしれませんね。
このように、GNSSの技術は日々進化しており、私たちの生活をさらに便利で正確なものに変えていくことでしょう。
まとめ

GISとは、断片的な地理情報を取得し、それを管理する、また管理したうえで様々な地図を提示するシステムのことでした。
日常に使うGPSでさえ、GISのおかげだと考えると、だいぶGISが身近なものに感じますね。
ぜひ皆さんもWeb上のGISを活用して、そのすごさを体感していただけたらと思います。
ここまでご覧いただきありがとうございました!
参考文献を載せておきます。ぜひご覧ください!



コメント