「柳田国男」という名前は、日本の近代を知る上で欠かせない存在です。
なぜ柳田国男は「日本の民俗学の父」といわれるのか?
それは、単に彼が「民俗学」という新しい学問分野を創始したというだけでなく、
その業績が多岐にわたり、後世に大きな影響を与え続けているからです。
今回は、柳田国男がどのような点で高く評価されているのか、その主なポイントを掘り下げていきましょう。
ストリートアカデミーとは?
ストリートアカデミーは「もっと哲学のことを知りたい」や「茶道や陶芸など新しい経験をしたい」という人たちにぴったりの講座がたくさんあります。
様々な体験をして、新しい自分になるための一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか?
「常民」の発見と、日本人の根源へのまなざし
柳田国男の最大の功績の一つは、歴史の表舞台に立つことのない「常民」、
すなわち普通の人々の生活や文化に光を当てたことです。
それまでの学問が、貴族や武士といった支配層の記録や、国家の大きな出来事を重視していたのに対し、
柳田は、農民や漁民、職人といった名もなき人々の日々の営みの中にこそ、日本人の本質や精神の源泉があると見抜きました。
彼は、全国を歩き回り、人々の暮らし、言葉、習慣、そして口伝えの物語に耳を傾けました。
この地道なフィールドワークを通じて、彼は「常民」が育んできた知恵や感情、信仰といったものが、いかに日本人のアイデンティティを形成してきたかを解き明かそうとしました。
この「常民」の視点は、これまでの学問にはなかった画期的なものであり、その後の日本研究に計り知れない影響を与えました。
『遠野物語』に代表される「物語」の価値の再発見
1910年(明治43年)に刊行された『遠野物語』は、柳田国男の代表作です。
この作品は特に彼の評価を決定づける重要なものです。
この物語を簡単にご紹介しますと、岩手県の遠野という山深い土地で、人々が語り継いできた「不思議な出来事」や「得体の知れないものたちの話」を、まるで昔話を聞くように淡々と紹介している本です
昔の「ゲゲゲの鬼太郎」のようなものと想像していただくと良いかと思います。
皆さんも河童、座敷童子など聞いたことがあると思いますが、そのような存在は「遠野物語」で紹介されました。
少しだけ下にご紹介します。
・河童や座敷童子の話: 沼や川に住むという河童や、家に福をもたらすという座敷童子など、日本各地で親しまれている妖怪や精霊の遠野バージョンが登場します。
・山人(やまびと)や山女(やまおんな)の話: 文明から離れて山で暮らす謎めいた人々との出会いや、恐ろしい山女の目撃談などが語られます。彼らは、人間とは異なる存在として、畏敬と恐怖の対象として描かれています。
・死者との交流や死生観: 亡くなったはずの人が現れる話や、あの世とこの世の境界があいまいな出来事が多く、遠野の人々がどのように死を捉え、生きていたのかが垣間見えます。
・怪異や奇妙な出来事: 人が突然姿を消したり、奇妙な音が聞こえたり、説明のつかない出来事の報告が多く、当時の人々の暮らしの中に、いかに非日常が溶け込んでいたかが伝わってきます。
・自然への畏敬: 山や森、川、沼といった自然が、ただの風景ではなく、様々な精霊や不思議な存在が宿る場所として描かれており、当時の人々が自然をどう捉えていたかを感じさせます。
詳しく知りたい方は『遠野物語』を実際に読んでみることをおすすめします。
次の本は「口語訳」なので分かりやすくなっており、おすすめです。
柳田国男の評価される点は、実はこれらの物語を単なる「迷信」や「お伽話」として紹介したからではありませんでした。
柳田国男は『遠野物語』のような物語には、人々の「心」や「生活の知恵」、それから「いかに自然と共生してきたか」というあり方が反映されているんだ、と主張しました。
明治維新を迎えた当時は「科学」が台頭し、目に見える数字や結果がより重視されてきました。
しかし、彼は、科学では割り切れない人間の「想像力」や、見えないものへの畏敬の念が、いかに人々の生活に根ざしていたかを明らかにしました。
もちろん『遠野物語』は、文学作品としても高く評価され、後の多くの作家や芸術家にも影響を与えました。
それは、科学信仰によって忘れ去られてしまうかもしれなかった日本の豊かな精神世界を、鮮やかに蘇らせた点で、極めて重要な意味を持っていました。
日本初の学問としての「民俗学」の体系化と確立
柳田国男が「民俗学の父」と称される最大の理由は、彼が民俗学という新しい学問分野を日本に確立したことです。
ただ、彼のすごいとことは、彼は単に各地の伝承を集めるだけでなく、それらを体系的に分類し、学問的な分析の対象としたことでした。
具体的には、以下のような点で評価されています。
- 広範な研究対象: 昔話、伝説、神話といった口承文芸から、年中行事、通過儀礼(誕生、結婚、葬儀など)、衣食住、信仰、祭り、方言、地名に至るまで、人々の生活全般を民俗学の研究対象としました。
- 独自の概念の提唱: 「常民」のほかにも、「ハレとケ」(非日常と日常)など、日本の文化や精神性を理解するための独創的な概念を提唱しました。
- 現地調査主義: 書物の研究だけである地方の過去を深堀しても限界があると気づいた柳田国男は丹念な聞き取り調査(フィールドワーク)から始め、詳細な研究をすることが大事だと主張しました。
- 研究対象の拡大: 地方の文化だけではなく、郷土の研究や民間の伝承、それから方言・言葉遣い、国語史(日本語)に関する研究など、現地調査を踏まえて、成果を発表しました。こうした研究は歴史学や国語教育にも影響を与えました。
これらの活動を通じて、柳田国男は民俗学を単なる趣味の領域から、学術的な厳密さを持つ独立した学問へと高めただけではなく、
歴史学・国語学にも多大な影響を与えました。
それからフィールドワークによる現地調査を受け継いだ人物もあらわれ(宮本常一など)、民俗学の発展にも寄与しました。
まとめ
柳田国男の業績は、決して過去のものとして終わっていません。
柳田国男は、単なる学者としてだけでなく、日本の近代化の波の中で失われゆくものに深い愛情を注ぎ、それを記録し、未来へと伝えようとした「実践者」でもありました。
彼の研究は、私たちが普段意識しない、足元にある日常の中にこそ、豊かな意味と知恵が隠されていることを教えてくれます。
さらに、民間伝承のような物語にこそ、真実が眠っていることを伝えてくれもします。
こうした点で柳田国男は今でも高く評価されているのだと思います。
ここまでご覧いただきありがとうございました。
以下は参考文献です。
(参考文献)
・『口語訳 遠野物語』(柳田国男=著、佐藤誠輔=訳、小田富英=注)
・『人と思想 199 柳田國男』(菅野覚明 =著)

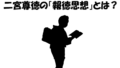
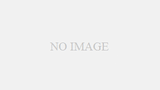
コメント