皆さんは浄土教をご存知でしょうか。
仏教には様々な宗派がありますが、その中でも「浄土教」は阿弥陀如来という仏様を信じ、
「南無阿弥陀仏」と念仏を唱えることで、死後に「浄土」と呼ばれる安らかな世界に生まれ変わる(往生する)ことを目指す教えです。
浄土教が日本の人々の間で広く受け入れられるようになった背景には、平安時代中期から末期にかけての社会情勢が大きく関係しています。
当時は、疫病や飢饉、戦乱(承平天慶の乱など)が相次ぎ、人々は現世の苦しみに深く絶望していました。
そんな時代において、難しい修行をせずとも、誰もが救われるという教えが浄土教であり、それは人々の心の拠り所となりました。
今回は、この浄土教の発展に大きな影響を与えた二人の僧侶、空也(くうや) と 源信(げんしん) に焦点を当て、彼らがどのように浄土教を広め、人々に希望を与えたのかを探っていきたいと思います。
ストリートアカデミーとは?
ストリートアカデミーでは、大人の学びなおし、子どもの学習のために様々な講座をお手頃価格で受けられます。
「もっと歴史や哲学のことを知りたい」や「茶道や陶芸など新しい経験をしたい」という人たちにぴったりの講座がたくさんあります。
様々な体験をして、新しい自分になるための一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか?
浄土教の基本的な教え
浄土教の根幹にあるのは、「他力本願(たりきほんがん)」という考え方です。
これは、自分の力(自力)で悟りを開くのではなく、阿弥陀如来の広大な慈悲の力(他力)に全てを委ねることで救われる、というものです。
そして、その他力を信じる心の表現として最も重要視されるのが、「南無阿弥陀仏(なむあみだぶつ)」と唱える念仏です。
そもそもこの念仏がなぜ重要なのか、念仏の意味を浄土との関係を踏まえて説明します
念仏の意味と、浄土とは?
念仏は「南無阿弥陀仏」と唱えることです(あるいは頭で念じることです)。
「南無」というのは今で言うと「あぁ」という祈りに似たものです。
「阿弥陀仏」は阿弥陀如来という仏のことです。
ですので、「南無阿弥陀仏」という言葉は、「阿弥陀仏に帰依します」という意味を持ちます。
では、阿弥陀如来とは何者なのか?
阿弥陀如来は「浄土」に住む仏とされています。
「浄土」とは、「穢土(現世=人が住む世界)」とは異なり、西方にあるとされている世界です。
具体的にはどのような世界かというと、しがらみがなく、人々が修行に励みやすい環境といわれています。
なぜ修行?と思われたかもしれませんが、仏教において修行するというのはとても大事なことです。
仏教のGOALは輪廻転生(=生まれ変わる)から脱すること=解脱することです。
解脱することは仏に成ること(=「成仏」すること)と同意とされています。
そのためには修行をして悟りを開くことが必要です。
修行をすることで生まれ変わり続ける世界から脱することができると考えているのです。
しかし、現実世界(穢土)では修行をしたいのに仕事や子育てとやることが多く、修行どころではありません。
さらに、いざ修行ができたとしても他のことを考えてしまいがちです。
すなわち、人間には煩悩があり、これを克服しないといけないのに、現実世界では難しいのです。
そこで、浄土教では、現実世界(穢土)では修行は難しいから、浄土というしがらみも何もなく、ただひたすら修行に励むことのできる世界にまずは行き、
そこで修行にはげんで解脱をしようという二段階のプロセスを踏もうとしています。
では、どうやって浄土にいけばいいのか。
そこで登場するのが、阿弥陀如来です。
阿弥陀如来とは?
阿弥陀如来は数々の如来(仏)の中でも最も慕われているといわれる如来(仏)です。
※そもそも「如来とは何か」については以下の記事に簡潔にまとめていますので、ご覧ください。
阿弥陀如来は立派に修行を重ねたので本来は「解脱(GOAL)」できるはずの人(仏)でした。
しかし、阿弥陀如来はこう思いました。
「まだまだたくさんの人が解脱できていない。私は皆(衆生)が解脱できるまで、浄土で待ち続けます!」
これは「弥陀の誓願」といわれるものを簡単に説明したものです。
弥陀の誓願とは、阿弥陀の願いのこと。(いくつもあるのですが、今回は一つだけご紹介しました。)
阿弥陀如来は「浄土」で衆生を待ち続け、皆が解脱できるように導いてくれる存在なのです。
だから、浄土(極楽浄土)とは、阿弥陀如来の住処ということになりますし、阿弥陀如来が皆さんを待ち続けている場所ということになります
では、衆生(一般の人たち)は何をすべきなのか。
それが念仏です。
「阿弥陀如来」のことを呼び続ける(思い続ける)ことで、阿弥陀如来の慈悲が衆生に届き、
同時に衆生の心が阿弥陀如来と繋がると信じられているからです。
具体的には念仏をすれば、浄土へ導いてくれるということに繋がります。
なぜ浄土教は広がったのか?
浄土教はなぜたくさん広まったのか、その理由を説明します。
その理由の一つは、口で念仏を唱えるというシンプルな行為が誰にとってもやりやすかったということがあげられます。
※一応、浄土教では唱えるだけでなく、心から阿弥陀如来を信じ、浄土への往生を願う心が伴ってこそ、念仏の功徳(くどく:善行によって得られる良い報い)は最大限に発揮されると考えられています。
一般的な仏教の厳しい戒律を守ったり、山へ修行に出て何日間も歩いたり、座禅を組んだりするといったものではなく、誰でもできる念仏は一般民衆に広まりました。
また、浄土教では、浄土へ往生するための修行は、これにより、身分の上下や性別に関わらず、すべての人が救いの対象となるという、画期的な教えが提示されました。
浄土教は、自力で修行をがんばらないといけないのではなく、
阿弥陀如来の力にお任せするという「他力」の宗教です。
そして、この教えを広めた有名な人物が、空也と源信でした。
「市聖」と呼ばれた遊行僧:空也上人
平安時代中期の日本において、浄土教を庶民の間に広める上で、絶大な影響力を持ったのが空也(くうや)上人です。
彼は一般的に「市聖(いちひじり)」あるいは「阿弥陀聖(あみだひじり)」と呼ばれ、その型破りな布教活動は、当時の人々に大きな衝撃を与えました。
空也上人の生没年は不詳な点が多いものの、彼は京都を中心に活動し、市中を行き交う人々や路傍に倒れる貧しい人々に寄り添いました。
当時の仏教は、貴族や権力者たちの間で広まることが多く、庶民にとっては縁遠い存在でした。
しかし、空也上人は、そんな既存の仏教の枠にとらわれることなく、自ら市井に下り、念仏を唱えることの重要性を説いたのです。
社会奉仕と念仏:行動する空也
空也上人は、念仏を唱えることだけでなく、具体的な社会奉仕活動を通して浄土教を実践しました。
彼は、道端に捨てられた死体を弔い、橋を架け、井戸を掘るといった社会基盤の整備にも積極的に取り組みました。
ちなみに火葬を広めたのも空也だと言われています。
これは、念仏が単なる口先だけの行為ではなく、困っている人々を救うという慈悲の心と結びついていることを示しています。
彼の活動は、当時の貴族社会の閉鎖的な仏教とは一線を画し、民衆の生活に深く根ざしたものでした。
空也上人の浄土教は、学問的な探求よりも、実践と行動を重視するものでした。
彼は、自らの身をもって念仏の功徳を示し、すべての人々が念仏によって救われることを、身をもって教え示した「生きた聖人」だったのです。
「往生要集」を説く源信僧都の思想
空也上人が実践的な布教活動で浄土教を広めたのに対し、源信(げんしん)僧都は、その思想的な基盤を確立し、後の浄土教発展に多大な影響を与えました。
彼は比叡山で天台宗を学び、学識に優れた僧侶でしたが、末法の世において、自力での悟りが困難であると感じ、浄土教の教えに深く傾倒していきました。
源信の代表的な著作が、寛和元年(985年)に著された『往生要集(おうじょうようしゅう)』です。
この書は、当時の人々が抱えていた現世の苦悩と、そこからいかにして救われるかという問いに対し、具体的な道筋を示した画期的な書物でした。
「往生」するとは極楽浄土で行くことを指します。
だから、『往生要集』とは極楽浄土へのガイドマップのようなものです。
特に源信が重要視したのが、次の「厭離穢土・欣求浄土」の思想です
厭離穢土・欣求浄土とは?
『往生要集』の根底にある思想は、「厭離穢土(おんりえど)・欣求浄土(ごんぐじょうど)」です。
- 厭離穢土(おんりえど):穢土は現実世界のこと。「厭離」とは「嫌だから離れましょう」という意味で、つまり、「穢れた世界、苦しみの多い現世(この世)は嫌だから離れましょう」という意味です。源信は、『往生要集』の中で、現実世界は地獄道や餓鬼道など、恐ろしい世界のありさまを具体的に描写することで、人々がこの現世の苦しみから逃れたいと強く願う心を喚起しました。疫病や飢饉、争いが絶えない世にあって、現世が苦しみの連続であるという認識は、当時の人々にとって非常に共感を呼ぶものでした。
- 欣求浄土(ごんぐじょうど):「欣求」は「心から求めよう」という意味です。欣求浄土は「安らかな浄土(阿弥陀如来のいる極楽浄土)を心から求めましょう」という意味です。源信は、現世の苦しみと対比するように、浄土の美しさや安らぎを詳細に描写しました。そこは、苦しみがなく、喜びだけがある世界であり、念仏を唱えることで誰もが往生できる場所であると説きました。
この「厭離穢土・欣求浄土」の思想は、すなわち、「穢土は苦しいので、浄土へいきましょう」ということです。
源信の『往生要集』はこの現実世界の苦しい点と浄土の美しさを詳細に描き、人々に理解しやすくした点です。
今でも、地獄のイメージは「鬼」とか「ドロドロしたマグマ」とかイメージされる人が多いと思いますが、
そのイメージを作り上げたのは源信の『往生要集』です。
人々が現世の苦しみから目を背けるのではなく、むしろその苦しみを深く認識することで、阿弥陀如来への信仰心をより一層深め、浄土への往生を切実に願う原動力となりました。
念仏の勧め
『往生要集』の中で、源信は、浄土へ往生するための具体的な方法として、ひたすらに念仏を唱えることを勧めました。
彼は、念仏の功徳について詳細に解説し、たとえ死の間際であっても、一度でも念仏を唱えれば、阿弥陀如来の慈悲によって救われると説いたのです。
また、源信は、念仏の他にも、阿弥陀如来の姿を心に思い描く「観想念仏(かんそうねんぶつ)」や、仏の功徳を心に留める「称名念仏(しょうみょうねんぶつ)」など、様々な念仏の方法を紹介しました。
しかし、最終的には、口に出して「南無阿弥陀仏」と唱える称名念仏が、誰にでもできる最も確実な往生の方法であると強調しました。
源信の『往生要集』は、難解な仏教の教義を分かりやすく体系化し、浄土教が単なる信仰感情だけでなく、理論的な裏付けを持つ教えであることを示しました。
この書は、当時の知識人層にも大きな影響を与え、後の法然や親鸞といった浄土宗・浄土真宗の開祖たちにも深く読み継がれ、日本の浄土教の発展に不可欠な役割を果たしました。
まとめ:時代を超えて響く浄土教のメッセージ
浄土教は、末法の世の苦しみの中で、人々が心の拠り所を求めた結果として生まれ、発展していきました。
そして、空也と源信という二人の偉大な僧侶の尽力によって、その教えはより多くの人々に届けられました。
空也上人の「踊り念仏」や社会奉仕活動は、仏教が一部の特権階級のものではなく、すべての人々のためのものであることを示しました。
彼は、身分や知識の有無に関わらず、念仏を唱えるだけで誰もが救われるという、希望のメッセージを体現したのです。
源信僧都の『往生要集』は、「厭離穢土・欣求浄土」という思想を通じて、現世の苦しみを直視し、そこから抜け出すための具体的な道筋を提示しました。
彼の著作は、念仏が単なる呪文ではなく、深い思想的背景を持つ教えであることを示し、後の浄土宗・浄土真宗の発展に不可欠な羅針盤となりました。
現代社会においても、私たちは様々な苦悩や不安に直面することがあります。
そんな時、空也上人のダイナミックな念仏の実践や、源信僧都が示した「現世の苦しみから離れ、安らかな世界を求める」という浄土教のメッセージは、私たちに心の平穏と希望をもたらしてくれるのではないでしょうか。
浄土教は今の時代にも安らぎと平穏をもたらしてくれる宗教だと思います。
ご覧いただきありがとうございした。
(参考文献)
・『大乗仏教―ブッダの教えはどこへ向かうのか』(佐々木閑=著)

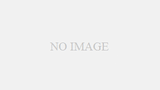

コメント