本日は、前5000円札の新渡戸稲造が記した『武士道』(①武士の持つべき徳目)について書いていきたいと思います。
『武士道』内で説かれている武士が持つべき徳目とは何なのか、
現代の日本人にも通ずる心得がありますので、ぜひご覧ください!
なぜ『武士道』を書いたの?

新渡戸稲造は、明治時代に活躍した日本の思想家であり、
国際連盟事務次長も務めた国際的な人物です。
彼が東京帝国大学に入学する際の面接で語ったとされる
「私は太平洋の架け橋になりたい!」という言葉は、まさに彼が生涯をかけて成し遂げようとした、
日本と世界(特に欧米)を平和的につなぐという強い意志を表しています。
後に国際連盟で活躍したことからも、彼が5000円札の肖像に選ばれたのは納得できますね。
『武士道』出版の背景
『武士道』は、新渡戸稲造が「日本を世界に伝えたい!」という強い思いを込めて著した作品です。
1900年に出版されたこの本は、当時の日本の国際的な立ち位置と密接に関わっています。
19世紀後半、欧米の先進諸国における日本のイメージは、
単なるアジアの東端にある「野蛮で幼稚な国」というものでした。
しかし、1894年の日清戦争で「眠れる獅子」と称された中国に日本が勝利したことで、
世界は日本に対し好奇の目を向けるようになります。
そんな折、新渡戸は一人の外国人から
「日本人は宗教教育がないそうだが、どうやって道徳を教えているのか?」と問われます。
この問いに対し、新渡戸は、
日本には宗教教育がなくとも、日本人が立派な武士道を備えており、
決して野蛮な民族ではないことを伝えたいという強い思いを抱きます。
そして、この思いから、
まずはアメリカに向けて英語で
『BUSHIDO-The Soul of Japan(武士道-日本の魂)』を出版しました。
この著作は異例の大ヒットとなり、
当時のアメリカ大統領セオドア・ルーズベルトが絶賛し、友人に配るほどでした。
その後、『武士道』は
ドイツ、フランス、ポーランド、ノルウェー、ハンガリー、ロシア、中国など
各国語に翻訳され、世界中で読まれることになったのです。
なぜこれほど読まれたのか、実際に『武士道』の中身に入っていきます
「武士道」はどのようにつくられたのか?
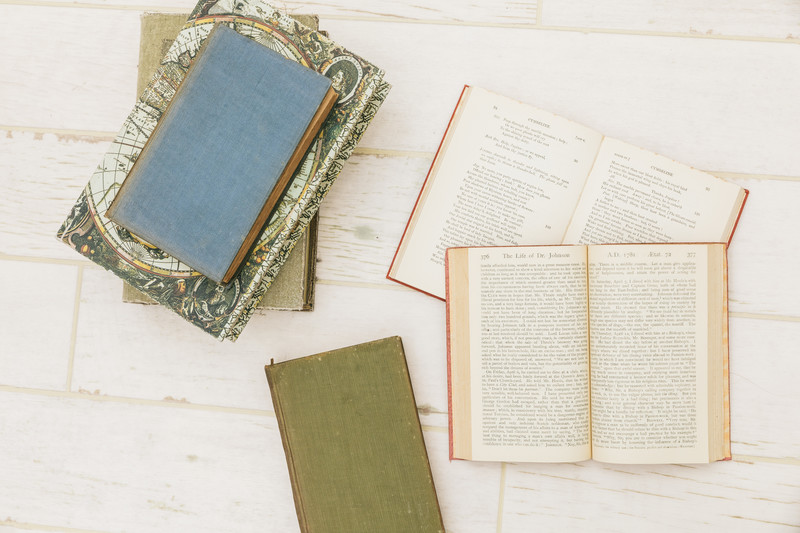
「武士道」がどのようにして日本に成立したのか、その明確な答えは一つではありません。
武士道は、特定の誰かが体系的に作り上げたものではなく、
鎌倉時代から江戸時代にかけての封建社会を生きた武士たちの間で、
長い時間をかけて形成された「武士のあるべき姿」が積み重なって生まれたものだからです。
武士とは元々、戦いを本業とする人々です。
彼らの中で培われた武士道には、時代ごとの義務や掟が組み込まれていきました。
その根幹には、儒教、仏教、神道といった日本の主要な思想や宗教の教えが深く影響を与えています。
武士道には、儒教、仏教、神道などさまざまな思想が深く影響している
武士道を形作った思想
特に、儒教の教えは武士道に最も多く取り入れられました。
具体的には以下のような徳目が挙げられます。
- 仁(じん): 他者への慈悲の心。
- 義(ぎ): 不正や卑劣を許さない、正しい道を選ぶ心。
- 礼(れい): 仁と義を具体的な行動として示す、節度ある振る舞い。
- 誠(せい)(または信):嘘偽りのない、誠実であること。
- 克己(こっき): 己の欲望や感情を抑え、自らを律する力。
また、仏教からは、常に心の平静を保つという精神が、
神道からは、主君への忠誠、祖先への尊敬、親への孝心(これは儒教の「孝」とも共通します)といった精神が、
それぞれ武士道の重要な要素として組み込まれています。
これらの武士道は、基本的に不言不文の掟、
つまり、文字として明文化されることのない、暗黙のルールとして代々受け継がれてきました。
それは、武士たちの日常生活や行動規範の中に息づく、生きた精神であったと言えるでしょう。
『武士道』が説く武士の徳目:日本精神の精髄

新渡戸稲造の著書『武士道』は、単に武士の義務や掟を羅列したものではありません。
彼は、武士道をフランス語の「ノブレス・オブリージュ(高貴な身分に伴う義務)」になぞらえながらも、
それを単なる抽象的な概念で終わらせず、具体的な徳目に分けて深く分析しました。
これにより、日本の精神性が世界に理解されやすくなったのです。
ここからは、『武士道』で新渡戸が解説した、武士を形作る主要な徳目を一つずつご紹介しましょう。
1. 忠義:主君への絶対的な献身
忠義とは、主君に対する服従と忠誠の義務を指します。
新渡戸は、この点において日本の武士に勝る国はないとまで述べています。
例えば、『菅原伝授手習鑑』という菅原道真にまつわる有名なエピソードがあります。
主君の子を斬るよう命じられた元家臣の松王丸は、なんと自分の息子を身代わりにするのです。
そして最後に「喜べ、われらの愛しき息子は立派にお役に立ったぞ!」と語ります。
これは、武士道においては、身内への愛情や孝行よりも忠義が何よりも重んじられたことを示しています。
さらに、この忠義は個人だけでなく、一族や家族が一体となって実践するものであり、
松王丸の息子もまた、自ら身代わりになる道を選んだとされています。
忠義は、個人が国家や主君のために生き、そして死ぬことも厭わないという境地を意味するかもしれません。
しかし、新渡戸は、これが「奴隷化」を意味するものではないと強調します。
もし国家や主君が誤った行為をした場合、
武士は自らの身をもって(時には命を懸けて)その過ちを正すこともありました。
その際に重要となるのが、次に述べる「義」の徳目です。
2. 義と勇:正しさを貫く精神
武士の掟の中で最も厳格な徳目とされるのが「義」です。
義とは、卑劣な行為や不正な振る舞いを決して許さず、正しいことを行う心、
いわば「正義感」に近いものです。
この義は、「忠義」を支える重要な柱でもあります。
そして、「義」の行動を実践するためには「勇」が必要不可欠です。
勇とはすなわち「勇気」のこと。
孔子が『論語』で「義を見てせざるは勇なきなり」と説いているように、
頭の中で正しいと理解していても、勇気がなければ実際に行動に移すことはできません。
例えば、電車でお年寄りに席を譲る行為が正しいと分かっていても、
なかなか実践できないのは、勇気が足りないからかもしれません。
一方で、「勇」は「義」のために行われるものでなければなりません。
命を投げ出す行為が全て勇気あるものに見えても、
死ぬに値しないもののために死ぬことは「犬死に」とされ、
武士の間では決して賞賛されるものではありませんでした。
つまり、「義と勇は常にセット」であり、両者が伴ってこそ真の武士道が発揮されると考えられていたのです。
3. 仁:慈悲と思いやりの心
「仁」は、慈悲の心、
すなわち他者への思いやりや優しさを指します。
特に為政者の心得として重んじられました。
鎌倉時代から江戸時代にかけて、
日本の将軍は基本的に世襲制であり、絶対的な権力を持っていましたが、
新渡戸は、それが専制政治ではなかったと指摘します。
その背景には、この「仁」の精神がありました。
日本の武士の間では、「勇気ある者はもっとも優しい者であり、愛ある者は勇敢である」
という考え方が普遍的な真理とされていました。
もちろん、すべての主君が「仁」の精神を完璧に体現していたわけではありませんが、
そうした主君に仕える側も、高い誇りをもって主君に従順していました。
これは、一見すると不思議な状態ですが、
日本の政治が世襲制で絶対的な主君を頂いていながらも、ある種の民主的な側面も持ち合わせていたと言えるでしょう。
4. 誠:言動と心の統一
「誠」は儒学では「信」とも表され、誠実さを意味します。
「武士に二言は無し」という言葉も有名ですが、これは単に嘘をつかないということではありません。
新渡戸は、誠実さを守るためなら、
日本人が「嘘」と捉えられるような配慮をすることもあると指摘します。
例えば、体調が悪くても相手に心配をかけまいと「元気です」と答えるような行為です。
つまり、誠実であることと、嘘をつかないことは別であると彼は考えました。
むしろ、一度決めたことを確実に実行することこそが「誠」であると強調しています。
そして、この「誠」は次に述べる「礼」を支える重要な徳目となります。
5. 礼:内面を映し出す外形
「礼」とは、「仁」や「義」といった内面の精神を外面的に表現したものであり、
一般に礼儀作法やマナーとして理解されています。
単なる形式的な動作ではなく、慈悲の心や正義感が伴った行動こそが「礼」なのです。
また、「礼」には「誠」が不可欠です。
心がこもっていない「礼」は、本当の礼儀とは言えません。
日本の「礼」は、その心配りの丁寧さゆえに、優美なものとなり得ました。
茶道に見られる繊細な作法は、もはや芸術の域に達しているとも言えるでしょう。
しかし、この日本独自の「礼」は、時に外国人にとっては不思議に映ることもありました。
新渡戸は、その例として二つのエピソードを挙げています。
- 日傘を下ろす日本人:暑い日に日傘を差していた男性が、知り合いの女性と会った途端、暑さにもかかわらず日傘を下ろして会話を続けました。女性はなぜ彼がそうしたのか不思議に思いました。
- 「つまらないものですが」と渡す日本人:アメリカ人が「素晴らしいプレゼントを素晴らしいあなたに」とプレゼントを渡すのに対し、日本人は「つまらないものですが、どうぞお受け取りください」と言って渡します。外国人は「つまらないものなら要らない」と思ってしまいます。
これらの行為は、日本人には理解できるものでした。
なぜなら、日本人の礼儀作法には「仁」「義」「誠」といった精神性が伴っているからです。
これは正直さとは異なります。
本音では「暑い」と感じたり、「素晴らしいプレゼント」だと思っていても、
それを表に出さず、感情や欲を抑制し、相手を立てる優しさを持つのが武士道の精神だったのです。
新渡戸は、日本人が世界の中でも最も優しい民族であるとまで述べており、
「おもてなしの国」日本は、まさに武士道の精神性の表れと言えるでしょう。
6. 名誉:命に勝る価値
「名誉」は、武士が最も重んじた徳目であり、命以上の価値があるとされていました。
簡単に言えば、「名をあげること」です。
武士の若者が得たいものは、富や知識よりもこの名誉でした。
母は、武士の子が家を出たら、名誉をあげるまでは家に帰らせなかったと伝えられます。
この名誉は「忠義」と密接に関係しており、主君のために命を張れるのも、この「名誉」への意識に由来していました。
逆に、名誉を汚す行為は「恥」とされ、武士は恥となる行為を避けることを心がけました。
すべては名誉のため。それが武士の生き方だったのです。
7. 克己:感情を律する忍耐
最後に、「克己」をご紹介します。
克己とは、己に打ち勝つこと、具体的には感情や欲望を抑制することを意味します。
武士は人前で大笑いしたり、泣いたりすることはありませんでした。
たとえ食べ物がなく貧困に陥っても、それに嘆き悲しむことは許されず、与えられた試練だと受け止め、
「忍耐」することが重んじられました。
克己の例として、外国人が不思議に思った事例があります。
- 悲しいのに笑う日本人:葬式の日、友人の奥さんが心配で駆けつけた外国人は、奥さんが悲しんでいるにもかかわらず、彼に笑って見せたことに驚きました。
外国人にとっては、「日本人は感情がないのか」「狂っているのか」と感じられるかもしれませんが、
そうではありません。
彼らが感情と異なる行為を外面で示すのは、心の平静を保つためです。
悲しいときに悲しみをそのまま外に出すと心が乱れてしまうため、
あえて笑顔を見せることでバランスを取ろうとするのです。
克己の理想は、いかなる状況でも心を平常に保つことにありました。
まとめ
武士の身に付けるべき徳目はいかがだったでしょうか?
全てではないにしろ、我慢強いところ、誠実さ、おもてなしの心など
現代の日本人にも通じる心があります。
②ではその武士道をさらに深めていきます。
特に「切腹」について取り上げていきます!
ぜひご覧ください!
ここまでご覧いただき誠にありがとうございました。
参考文献もぜひお読みください!




コメント