こんにちは。よっとんです。
歴史・倫理哲学・心理学、それから本紹介のブログを書いています
今日は「一揆の種類【わかりやすく解説】」という話です。
皆さんの中には
- 土一揆・国一揆・一向一揆の違いがよくわからない!
- そもそも一揆とは何なのかわからない!
という方がいると思います。
この記事は代表的な一揆の細かな内容は抜きにして、
とりあえず土一揆とは何なのか、国一揆とは何なのか、一向一揆とは何なのか?
という点だけに焦点を絞って解説しています。
長く書かない!!ということを意識しましたので、
とても簡単に読むことができると思います
ぜひ最後までご覧ください!
土一揆とは?(惣とは?)
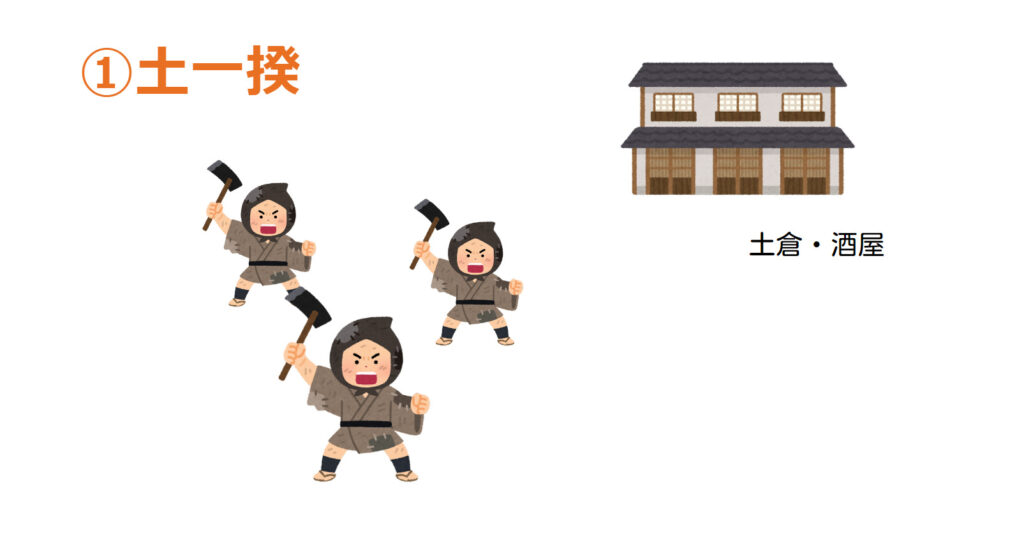
土一揆とは、土民の一揆です。
土民とは、主に農民(百姓)のことです。
当時の支配者が一般庶民(農民)を見下して総称したものを「土民」と言いました。
そんな土民たちがなぜ一揆をおこすようになったのか、
それを知るには室町時代から農民たちがつくりあげた惣村についての解説が必要ですので、
そちらを先に説明します。
惣(惣村)とは?
惣(惣村)とは、農民たちによる自治的な組織のことです。
イメージ的に言えば今の村ですね。
鎌倉時代の農民たちは血縁的な結合(=家族や親せきのつながり)が強く、
あまり、大きな規模の組織はできませんでした。
しかし、鎌倉時代後期になると地縁的な結合(=その土地に住んでいる人たちのつながり)が強まります。
なぜそうなったのかの細かい理由はここでは省きますが、
簡単にいえば、元寇、すなわち元という国が日本を襲ってきた出来事(日本にとっての防衛戦)で、
日本は見事勝利したものの、
土地がもらえなかった(防衛戦で土地は増えなかった)ので、
この事件以降、血縁関係の中での土地の分割相続(みんなで平等に分ける)が難しくなったからです。
それにより血縁関係は解消され、地縁的な結合が強まりました。
さらに鎌倉時代後期や室町時代は戦乱が多い時期でもあります。
将軍が何度も守護大名を追放したり、将軍が暗殺されたりすることが重なります。
そこで農民たちは、自分たちの身は自分たちで守ろうと思うようになります。
そうしてできたのが「惣」という、農民たちによる自治的な組織でした。
どの辺が自治的なのかというと、
まず、自分たちで話し合い(※「寄合」といいます)ルールをつくります。
これを「惣掟」といいます。
これを破る者が現れたら、自分たちで罰します。これを「地下検断(自検断)」といいます
あとは、農民たちで祭祀をおこなったり(「宮座」という)、
共同作業(「結・もやい」という)や税の一括請け負い(地下請)も行いました。
このように、室町時代は自治的な組織である、「惣(惣村)」ができあがっていたのです。
愁訴?強訴?土一揆?
では、土一揆に話を戻します。
土一揆は土民たちの一揆です。
主人公は惣村の農民たち(土民)です。
なぜ一揆を起こしたのか、理由はさまざまです。
例えば、税金を徴収する代官や荘官の悪行を行った場合、金貸しの酒屋や土倉の悪行が目に余る場合などです。
最初は要求内容を紙にして訴える形をとりました。これを愁訴といいます。
しかし、これではいうことを聞かない人たちもいます。
こういう時は実力行使です。
集団で押しかけて訴えることもしました。これを強訴といいます。
また、ストライキもありました
農民たちが耕作地から逃げ出す(徴税できな状態にする)こともありました。これを逃散といいます。
一揆とは、これらのうちの強訴の強化バージョンと思っていただければと思います。
つまり、実力行使で訴えるだけではなく、襲撃(武力行使)も行うものが一揆です*。
特に、土一揆は「徳政令」を発布させることを目的としたものが大半でした。
畿内のみで私徳政を出すことに成功した「正長の土一揆(徳政一揆)」(初めての土一揆)
幕府が徳政令を発布に至った、「嘉吉の土一揆(徳政一揆)」というものが代表的な例になります。
以上が土一揆の説明でした。
*本来「一揆」は一致団結すること(盟約を結び、行動をともにすること)を意味しましたが、しばしばその行動が武力蜂起の形をとったので、そうした意味に変わっていきました。
国一揆とは?
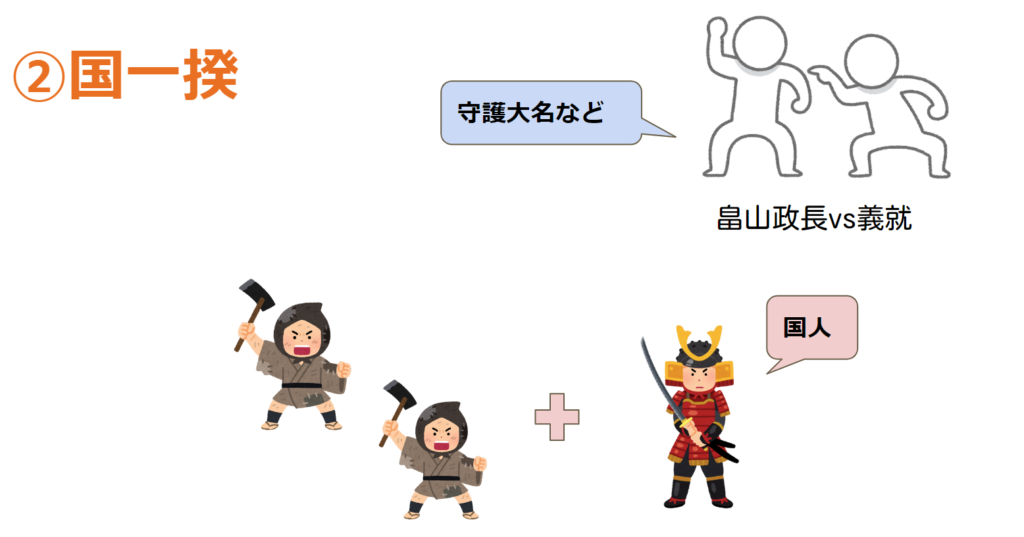
それでは続いて国一揆の説明に移ります。
国一揆は、さきほどの土一揆に国人が加わり、規模が国単位になったもののことを言います。
簡単に言えば、土一揆の拡大バージョンです。
土一揆の主体は土民(主に農民)でしたが、国人は武士です。
武士といっても守護大名や戦国大名のようなとても力のある武士ではなく、
地方に在住する武士です。
地頭(武士の中で徴税をする役職)などの領主も当時は国人と呼ばれていました。
国人は元々自立の気質が強く、守護は彼らを家臣化することに手をこまねいていました。
今風でいえば、地元のヤンキーですね。
その地元のヤンキーと地元(惣村)の農民たちが一致団結して、守護大名などを倒そうとした一揆、
それが国一揆というものになります。*
他方、国一揆は、国人+土民の一揆です。
代表的な国一揆は、山城の国一揆、伊賀惣国一揆などがあります。
*国人一揆と国一揆は異なります。
国人一揆は国人たちが守護に対抗するため、あるいは農民たちの抵抗を抑えるために結びつくこと、
すなわち一致団結すること(=一揆)をいいます。
(地元のヤンキーがシマを抑えるためにヤンキー同士で手をくむイメージです。)
一向一揆とは?
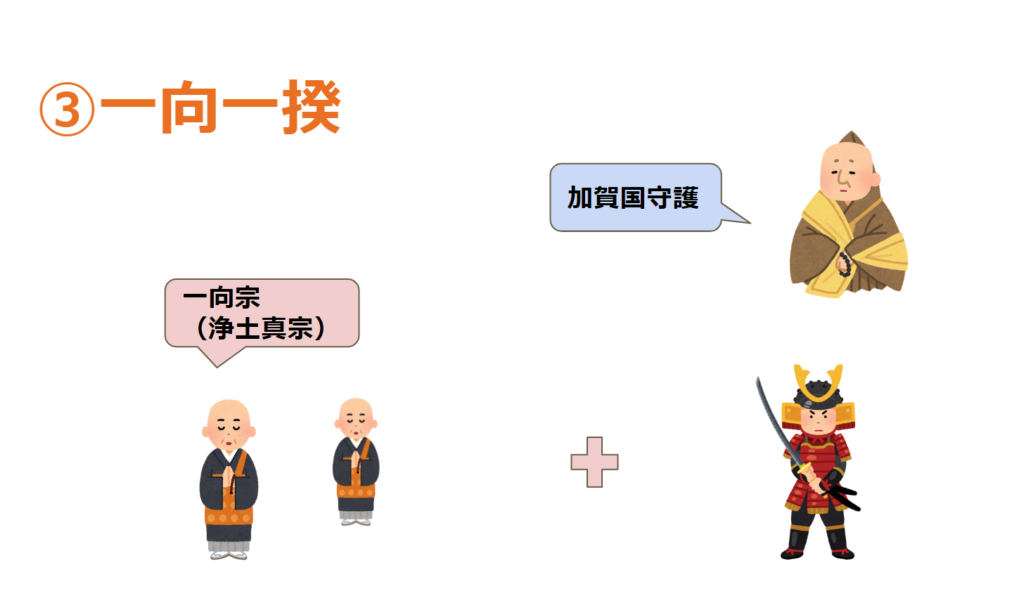
最後に一向一揆ですが、これは今までとは異質の主人公です。
一向一揆の一向とは一向宗のことです。
一向宗とは親鸞が始めた浄土真宗のことです。
つまり、一向一揆の主な主人公は浄土真宗の宗徒ということになります。
もちろん、国人や土民が加わることもありました。
宗教的な結びつきはとても強く、代表的な加賀の一向一揆では、
加賀の守護富樫政親を倒すことに成功し、約100年間の自治を獲得しました。*
ほかにも宗教的な結びつきによる一揆はあります。
例えば法華一揆。
これは法華宗、すなわち、日蓮がはじめた日蓮宗の宗徒による一揆です。**
こちらの法華一揆も室町時代後期に特に猛威を振るました。
一向一揆と対立も起こし、山科本願寺(一向宗側の寺)を焼き払うことまでしています。
このように一向一揆、法華一揆などの宗教的な一揆はとても強い効果を発揮しました。
*加賀の約100年間の自治を終わらせたのは織田信長でした。
**日蓮宗では「南無妙法蓮華経」と唱える「唱題」がありますが、
この中の「妙法蓮華経」は略して「法華経」といいます。これが法華宗の由来です。
まとめ
一揆の違いはいかがだったでしょうか。
最後にまとめておくと
- 土一揆は「土民」(主に農民)の一揆
- 国一揆は「土民」+「国人(地方在住の武士)」の一揆
- 一向一揆は「一向宗」の一揆
でした。
もちろん、土一揆の中に武士が混ざることも、一向一揆の中に土民が混ざることもありますが、
あくまでも一揆をおこした主体は誰だったかという視点で見ていただければと思います。
以上、「一揆の違い【わかりやすく解説】」でした。
他の記事も細かすぎず、すらっと読めるような記事がたくさんありますのでぜひご覧ください!
ここまでご覧いただきありがとうございました!
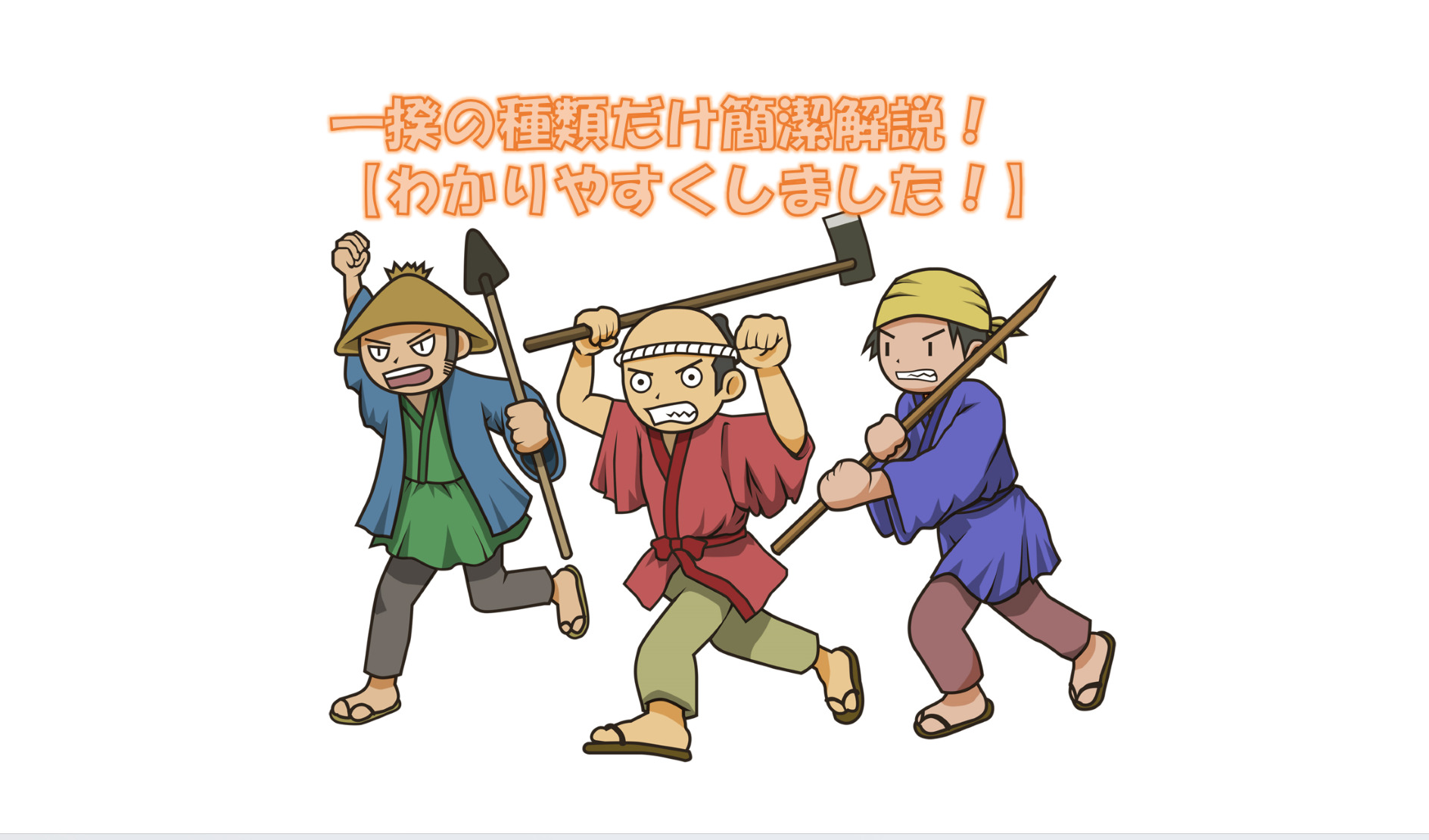

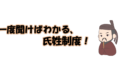
コメント