「誰でも幸福になれるし、ならなくてはならない。しかし幸福になるのは簡単ではない」
—これは、フランスの哲学者アランがその主著『幸福論』で語った言葉です。
本名エミール・オーギュスト・シャルティエとして
1868年にノルマンディー地方で生まれたアランは、高校で哲学を教え、
新聞に掲載されたエッセイ「プロボ」の中から幸福に関するものを集めて『幸福論』を著しました。
この美しい散文詩集のような哲学書は、「幸福は徳である」と説き、
私たち自身が幸福になることが世の中にとっても良いことだと教えてくれます 。
ストリートアカデミーとは?
ストリートアカデミーでは、大人の学びなおし、子どもの学習のために様々な講座をお手頃価格で受けられます。
「もっと歴史や哲学のことを知りたい」や「茶道や陶芸など新しい経験をしたい」という人たちにぴったりの講座がたくさんあります。
様々な体験をして、新しい自分になるための一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか?
不幸のメカニズムと対処法
アランは、
「不幸になったり不満を覚えたりするのはたやすい。ただじっと座っていればいいのだ。人が自分を楽しませてくれるのを待っている王子のように」と指摘します。
気分に任せて生きている人は悲しみにとらわれ、やがていら立ち、怒り出すと警鐘を鳴らします。
例えば、電車が遅延したときに、ただ座ってイライラしているだけでは、状況は改善せず、気分は悪くなる一方です。
自分の不幸を他人のせいにしてしまいがちですが、
その根底には自分が不幸であるという認識があり、それが他人への暴力につながることもあるといいます 。
しかし、不幸とは「その状況の自分の気分をどう解釈するか」にかかっています。
気分を野放しにすると不幸に吸い寄せられるため 、アランは具体的な対処法を提案しています。
問題の真の原因を見つける
アランは、幼子が泣いている例を挙げます。
乳母は両親の育て方や恐怖を想像しますが、
よく見るとピンが赤ん坊に刺さっていたという物理的な原因が見つかります。
このように、困難も不幸も本当の原因さえわかっていれば、
対処法はさほど難しいことではないのです。
例えば、仕事でうまくいかない時、
漠然と「自分が無能だからだ」と悩むのではなく、
具体的に「情報収集が足りなかった」「段取りが悪かった」など、
具体的な原因を探ることで、次への具体的な対処法が見えてきます。
ネガティブな感情が湧きおこったら、まずはその感情が湧きおこった原因を見つけよう!
不機嫌に無関心でいる
私たちは何か問題を抱えた時、ずっとその問題に悩んでしまうことがあります。
モヤモヤした感情がずっと頭から離れない時、アランの言葉が役に立つでしょう。
「幸福の秘訣のひとつ、それは自分の不機嫌に対して無関心でいることだと思う。相手にしないでいれば、不機嫌などというものは犬が犬小屋に戻っていくように、動物的な生へと舞い戻っていく」
犬はかまうとじゃれてきますが、放っておくと静かに犬小屋へ帰るように、
不機嫌も同じように放っておけば静まるというのです。
例えば、朝からなんだか気分が乗らない日でも、その不機嫌を意識しすぎず、
あえて無視して普段通りに活動することで、いつの間にか不機嫌が解消されていることがあります。
アンガーマネジメントでも、怒りの感情が起こったら、感情が収まるまで待ってみるという対処法があります。
怒りの感情は時間の経過とともに和らぎます。
その他のネガティブな感情も無関心でいれば、いつか忘れるという気概を持つことが必要かもしれません。
ネガティブな感情から目を背けることも時には大事!
身体的なケアの重視
人がいらだったり、不機嫌だったりするのは、
しばしばあまり長く立ち通しだったせいであるとアランは指摘します。
そんなときはあれこれ理屈をこねるのではなく、椅子を差し出してやるのが良いとしています。
これは、身体的な状態が気分に影響を与えることを重視している点で、
ヨガのように体をリラックスさせることが重要だとしています。
休息、深呼吸、体操、ほほえみ・あくび・伸び
などが精神のこだわりをほぐすのに役立ちます。
アランの言葉で特に有名なのが、次の言葉です。
「幸せだから笑うのではない、笑うから幸せなのだ」
私たちの感情は身体的なものにとても影響を受けます。
例えば、ストレスを感じて頭が煮詰まっているときに、
いったん席を立って深呼吸をしたり、軽くストレッチをしたりするだけで、
気分が切り替わり、問題解決の糸口が見つかることがあります。
イライラしたりしたときは、身体の緊張をほぐす行為をしましょう。
ネガティブな感情が起きたら、意識的に身体を休ませよう!
情念との向き合い方
喜怒哀楽といった「情念」は、私たちを不幸に陥れるものですが、
否定すべきものではなく、溺れてもいけないとアランは説きます。
情念は私たちの性格や思想から起因するように見えながら、
どうにも打ち勝てない必然性を帯びており、
対象が目の前に無くても愛したり憎んだりできるため、私たちはなすすべがないと感じてしまいます。
情念は想像の中で膨らんでいく自分の感情であり、
自然の法則、社会の慣習、他人の存在、そして死といった自分の自由にならないものに影響されます。
アランは、自身が反戦主義者でありながら第一次世界大戦に従軍した経験から、
「戦争を生み出す社会」を指摘し、
「私の情念、だが、私よりも強い」という状況に対して「意志の力」の重要性を強調します。
彼は「悲観主義は感情で、楽観主義は意志による」と述べ、
「幸福になりたいと思ったらそのために努力をしなければならない」と説きます。
例えば、将来への漠然とした不安(情念)に襲われたとき、ただ不安に浸るのではなく、
具体的に何ができるかを考え、資格の勉強を始めるなど、意志的な行動を起こすことで、
その不安を乗り越え、楽観的な展望を開くことができるのです。
ネガティブな感情に取り込まれる前に、意志をもって行動を起こそう!
行動と人生の主役
「喜びは行動とともにやってくる」という言葉が示すように、行動なしには幸福は得られません。
アランは「人間は行動のない快楽よりも、行動に伴う困難のほうを選ぶ」と述べ、
「人生の主役になれ」と私たちを鼓舞します。
子ども時代に人形劇をした例を挙げ、
他人の芝居は退屈でも、舞台役者なら退屈しないように、
喜びは自分で見つけ出すものであり、人生の主役になることで得られるのだと説明しています 。
「どんな職業も自分が導く限りでは愉快だが、服従する限りでは不愉快である」という言葉や、
「山頂まで登山電車で来た人は、登山家と同じ太陽を見ることはできない」という比喩は、
自ら行動し、困難を乗り越えることの重要性を示しています。
例えば、新しいスキルを身につけるために、言われた通りに講義を受けるだけでなく、
自ら課題を見つけて積極的に実践したり、応用的なプロジェクトに挑戦したりすることで、
より深い満足感と喜びを得られる、ということです。
行動こそが幸福への第一歩!
礼儀正しさの力
アランは「礼儀正しさ」も幸福に深く関わると考えます。
レストランで不機嫌な人がいると、
その場の空気が悪くなり、周りの客や店員にも影響を与えるように、
不機嫌は伝播します。
アランは礼儀をダンスに例えます。
ダンスの初心者は教本通りに踊ろうとしますが、
それだけでは相手と呼吸が合わず、ギクシャクしてしまいます。
上級者は自然体で呼吸を合わせられるように、
礼儀も硬くなったりせず、穏やかに自然体でいられること、
無駄のない洗練された動きや感情のコントロール、そして相手に合わせていくことが重要だと説きます。
フランス語のPolitesse(礼儀)が「しなやか」や「自分」を意味するように、
自然な物腰は処世術であり、生活知であり、習慣となるものです。
さらに、自分自身に対しても礼儀正しくあるべきだとし、
「無作法な人間は一人でいるときでもやはり無作法である」と指摘します。
例えば、自宅で一人でいる時でも、だらしない格好や態度でいると、
気分が沈んだり、行動も億劫になったりすることがあります。
しかし、身なりを整え、姿勢を正すだけで、自然と気持ちも引き締まり、前向きになれることがあります。
礼儀正しく常にいることは不幸を遠ざけることにもなる!
憐れみと信頼
相手への憐れみや同情は、不幸や悲しみを増幅させることがあります。
アランは
「悲しんではなるまい。期待を持つべきなのだ。人は自分の持っている希望しか、人にはやれないものだ」
と語り、生命の力を信じることの重要性を説きます。
元気になれという励ましでもなく、ただ生命の力を信じることです。
彼は、
「実際彼を憐れみすぎてはなるまい、冷酷かつ無関心であれというのではない。そうではなくて快活な友情を示すことだ。誰も人に憐れみを引き起こさせることは好まない。もし自分がいても健康な人間の喜びを消し去りはしないということが分かれば、彼はたちまち立ち直り、元気が出る。信頼こそすばらしい妙薬である」
と述べます 。
同情という情念に流されるのではなく、
信頼や快活さ、友情、希望といった本質的な力に導かれるべきであり、
自分の幸福と相手の不幸の差を気にする必要はありません。
何よりも、自分自身が幸福でないと、他人に幸福を与えることはできないのです。
そのため、自分の不幸を他人に話さず、他人に言われた悪口を気にせず、
他人を束縛しないことが大切です。
例えば、友人が落ち込んでいる時、ただ一緒に悲しむだけでなく、
「君ならきっと乗り越えられるよ」と信頼の言葉をかけ、明るい話題を提供したり、
一緒に楽しい時間を過ごしたりすることで、友人が元気を取り戻すきっかけを作ることができるのです。
人を幸福にしたいなら、自分こそが幸福でいること!
人間関係と「哲学する」生き方
アランにとっての人間関係は、
果物一個であってもおいしくなるように工夫できるものであり、
結婚生活やその他のあらゆる人間関係についてはなおさらであると述べます。
人とのつながりはその時の天気や風向きによって
快適だったりそうでなかったりするような木陰のようなものではなく、
魔法使いが雨を降らせたり、天気にしたりする奇跡の場所であるとしています。
アランは「自分のことを考えるな。遠くを見よ」と語り、物事のことを気にしすぎるのではなく、
目というものは近くのいざこざを見るためではなく、遠くをみるためにあるのだと指摘します。
人間関係における理想は、「お互いの本性を認め、相手が自分自身であり続けるのを求めること」、
つまり「その人があるがままの姿であるのを望むこと、それが真の愛である」と結論づけています。
そして、アランが提唱するのは「哲学する」という生き方です。
これは、ただ哲学を理解したり考えたりするのではなく、実践することです。
「要するに幸福に関しては、推論することも予見することもできないのである。今現にもっていなければならない。」
もし幸福が未来にあるように見えるなら、それはすでにあなたが幸福を持っている証拠であり、
「希望すること、それは幸福であるということなのだ」とアランは締めくくっています。
まとめ
アランの『幸福論』は、幸福が受け身で得られるものではなく、
自らの意志と行動、そして日々の実践によって築かれるものであることを教えてくれます。
不幸の原因を突き止め、不機嫌に惑わされず、身体的なケアを怠らず、情念をコントロールし、
人生の主役として行動すること。
そして、礼儀正しさを身につけ、他者との関係においても相手を尊重し、信頼すること。
これらすべてが、私たちが「今、ここに」幸福を見出し、希望を抱いて生きていくための指針となるでしょう。
ぜひアランの『幸福論』を一読していただけたらと思います。
・アラン『幸福論』
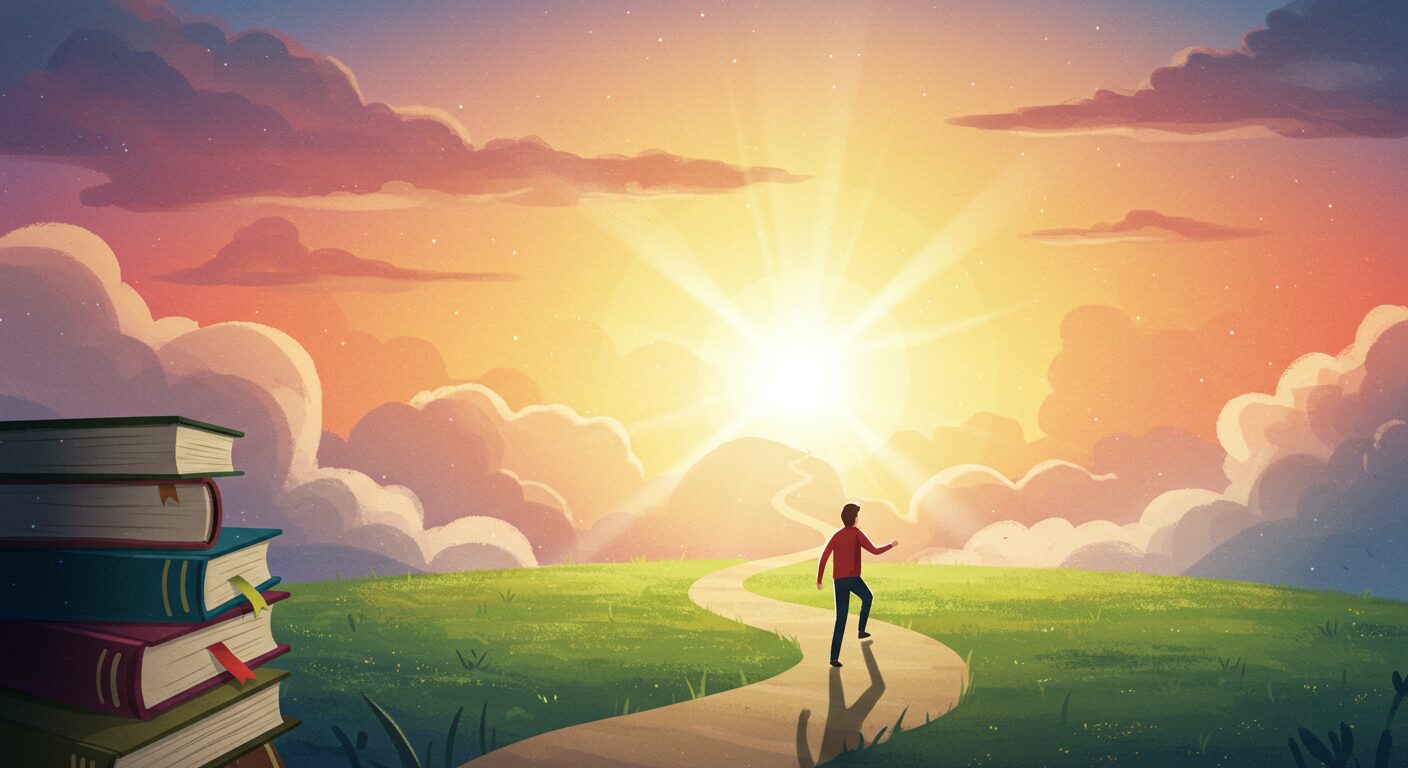


コメント