今日は夏目漱石の哲学についてお話しします。
このブログでは以下のことが分かります。
- 夏目漱石の「自己本位に根差す個人主義的な生き方」とは何か?
- 晩年の夏目漱石が至った境地「則天去私」とは?
では見ていきましょう!
夏目漱石を簡単にご紹介!
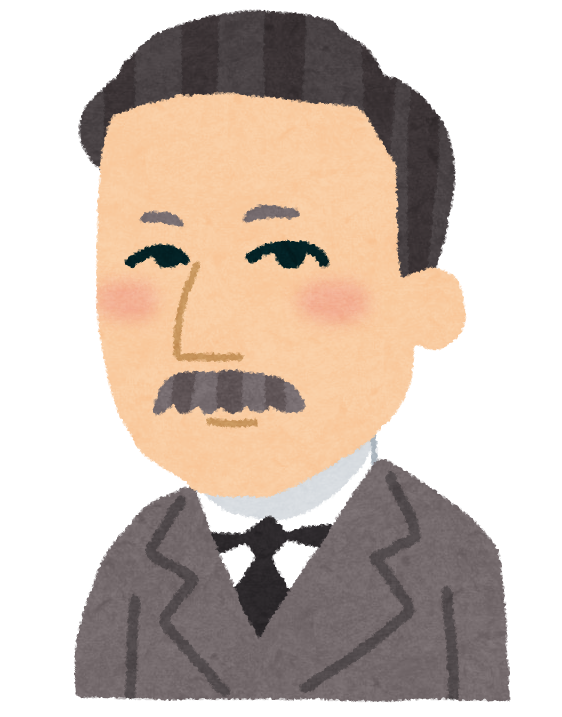
夏目漱石は、名主の末子として牛込馬場下(現東京都新宿区)に生まれました。
1歳の時に養子に出され、9歳の時に養父母の離婚が理由で、夏目家に戻ります。
この養父母との関係は、のちに自伝的小説である『道草』で表現されています。
養父母は漱石を大事に育てていた(束縛が強かったということでもあります)ので、
漱石を手放したくなく、21歳まで籍が変わりませんでした。
漱石はずいぶん複雑な環境で育ったのですね。
実の親の愛情を受けられなかった寂しさもあったかもしれません。
その寂しさ・孤独感が後の漱石の思想に関わってきます。
そんな漱石は漢詩が得意で文学的才能に恵まれたこともあり、
東京帝国大学で英文学を学びます。
30歳になった漱石は熊本第五高等学校の英語講師として働いていました。
そんな漱石に転機が訪れます。
文部省から、現職のまま国費でイギリスに留学を命じられたのです。
きっと漱石は大きな期待をもっていたと思います。
しかし、イギリス留学は彼の期待を裏切るものでした。
文明化・近代化しているイギリス。
外面的には華やかでした。
ただ、人々の心はとても冷たい。
彼は孤独感を感じてしまいます。
しまいにはノイローゼになり、帰国を余儀なくされました。
近代化は幸せに繋がるわけではないのか・・・
漱石は、小説の中で文明化と孤独感について述べています。
文明は我々をして孤独せしむるものだ
『それから』
自由と独立と己とに充ちた現代に生まれた我々は、
『こころ』
その犠牲としてみんなこの淋しみを味わわなくてはならない。
この孤独とどう立ち向かったのか、それが漱石の思想のメインテーマの一つでした。
漱石の思想

漱石は西洋の文明化に孤独を感じました。
文明が孤独というのは現代の我々も感じることなのではないでしょうか
例えば、携帯が普及したことによってわざわざ人に会うことをしなくなりました。
村文化や町文化を肌で感じることもなく、人の温かさに接する機会も減ったように感じます。
漱石の生きた明治時代は江戸時代から大幅に変化した時代でした。
江戸期の頃の集団や家族・血縁で仕事をする風習は廃れていき、
個人で労働者として働きに行くことが増えていきました。
また、明治期は自由が提唱されるようになりましたが、
逆にいえば、個々で進学先・就職先・結婚相手などを選択して生きなくてはならない時代でもありました。
こういったとき、どうしても哲学者のサルトルの言葉を思い出します。
人間は自由の刑に処せられている
『実存主義とは何か』
自由という重い責任が私たちを孤独へ追いやる。
こういった西洋の個人主義に、漱石は孤独感を抱いたと思われます。
そんな孤独感から漱石はどうやって立ち直ったのでしょうか?
それが、次に示す「自己本位に根差す個人主義」という思想でした。
「自己本位」とは?

漱石の見出した「自己本位」とは何か?
それは、「自分を大事にし、自由に生きる」という意味です。
簡単に言えば、「自分を尊重していい」という考え方です。
例えば、進学先を決めるとき。
あなたは、自由に選択できる世の中にいますので、進学先を迷うことがあるかと思います。
「この進学先で合っているのかな?人生を無駄にしないかな?」と不安になるかもしれません。
でも、その選択をした自分を肯定していいのです。
あなたが選んだ進学先は、あなた以外の人ではなく、あなたが肯定すべきなのです。
漱石は、このように自分の選択したものや自分の立場を肯定する在り方を
「自己本位に根差す個人主義」と言いました。
これは、利己主義とは異なります。
利己主義とは、自分勝手に生きる、わがままに生きることです。
この場合、他人の生き方よりも自分の生き方を優先することになります。
一方で、「自己本位に根差す個人主義」は「自分を肯定しているあり方自体を尊重する」ものですので、
他者をも尊重する思想ともいえます。
なぜなら、他の人の人生もその人自身が肯定した結果(経験)ですから、その人の自由を脅かす行為はいけません。
すなわち、自身の人生を肯定しているもの同士、尊重しあえるものなのである、
これが漱石の「自己本位に根差す個人主義」の考え方でした。
自己も他者も尊敬する「自己本位に根差す個人主義」という在り方を漱石は見出したとき、
彼はとても自信を持てたそうです。
私はこの自己本位という言葉を自分の手に握ってから大変強くなりました。
『私の個人主義』
さて、この考え方を手に入れた漱石はその後、自己に忠実に、そして自由に生きることを決意します。
しかし、漱石の「自己本位に根付く個人主義」的な生き方には限界がありました。
その理由も含め、彼が最終的にどのような立場をとったのか、次で見ていきましょう
則天去私の境地
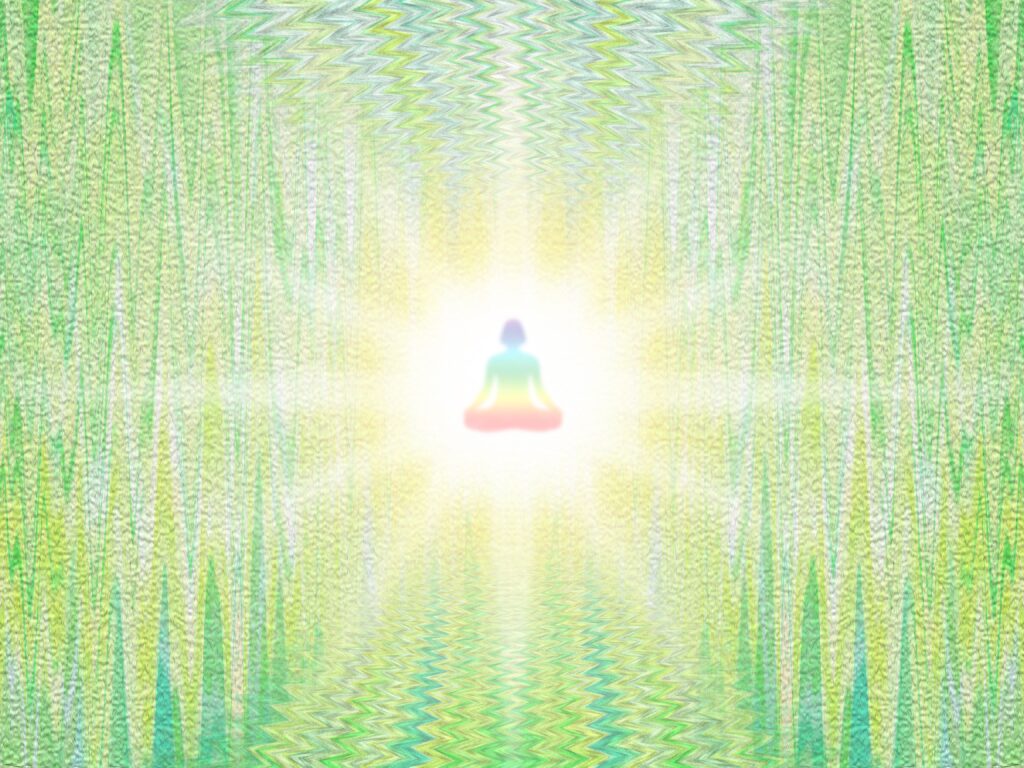
漱石にとって「自己本位に根差す個人主義」という在り方は自信になったことは確かでしたが、
そのような個人主義的な生き方は、社会的・国家的な要請や「常識」と何度もぶつかることにもなりました。
「自分はこうしたい・・・でも社会的にはNGである」
これは、現代の我々も理解できると思います。
「自分はこういう性として生きたいが、まだまだ社会的に生きにくい・・・」
「本当は○○大学に行きたいが、将来のことを考えると名門の△△大学に行かないといけないかな…」
などもそうですね。
漱石もこうした矛盾に何度も苦痛を強いられました。
特に、彼の生きた明治末~昭和初期は、戦争や経済不況が続く時代でもありましたから、
そうした激動の時代の中で、漱石の個人主義的な生き方は限界を迎えてしまったのです。
では、彼は晩年どういった思想を展開したのか・・・
それが、「則天去私」です。
「私を去り、天に則る」という考え方です。これは漱石の造語です。
「無我は大我と一なり、故に自力は他力に通ず」と漱石が記しているように、
東洋の禅思想に近いもので、無我の境地や自我を超越したあり境地を指します。
ここでの「私」とは「エゴイズム」のことを指し、
簡単に言えば、「エゴイズムを捨て去って、自然(天)に全身をゆだねる生き方をしよう!」という意味になります。
理解はできますが、なかなか実感はわきませんね(笑)
最晩年にこの境地を自覚した漱石は実践的小説として『明暗』を描きました。
しかし、この小説は未完に終わってしまい、その詳細は不明のままです。
ここからは個人的な予想ですが、
漱石は、「私心を捨てて、自然の道理に生きる」という宗教的な境地に至ることで、
個人主義も孤独感も乗り越えた思想を展開したかったのかもしれません。
そうして、孤独感や社会的な圧力から自分を解放しようとしたのかもしれません。
まとめ
漱石の哲学はいかがだったでしょうか。
はじめは、孤独感を否定するために、「自己本位に根差す個人主義」を見出し、自信を得た漱石でしたが、
社会的な圧力や国家的な要請と衝突を引き起こすことで、個人主義の限界を感じました。
そして、最終的には則天去私の境地、すなわち、自然の道理に任せてしまうというありかたで自己を救済しようとしました。
そんな彼の生きざまや思想は小説の中に多く表現されています。
以下、おすすめの小説を載せておきますので、ぜひ彼の小説をお読みになることをお勧めします!
最後までお読みいただきありがとうございました!
★おすすめの小説
・『こころ』
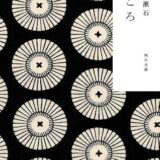
・『草枕』
・『三四郎』
★参考文献
・『私の個人主義』(著者:夏目漱石)
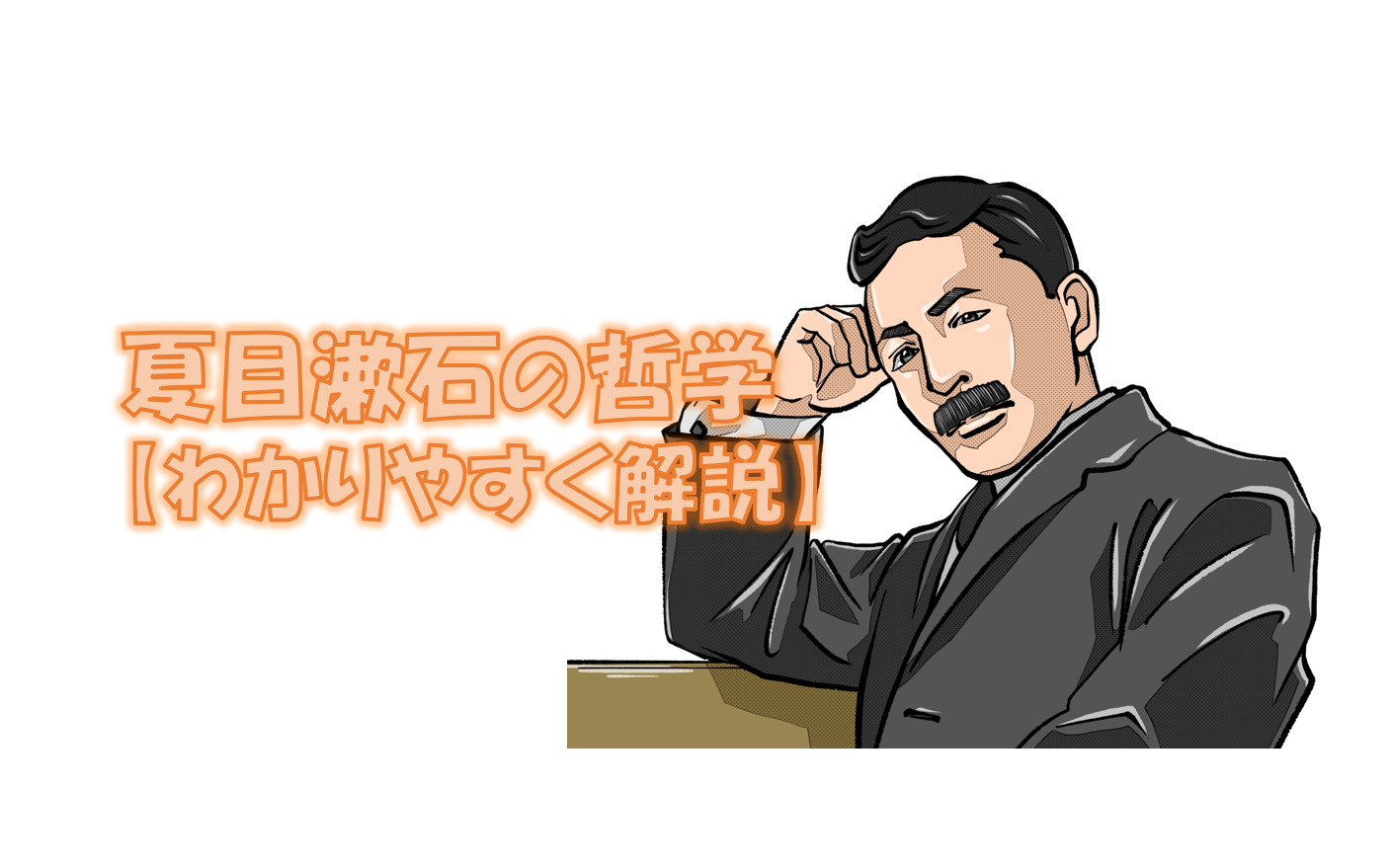

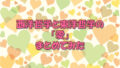
コメント