明治から昭和にかけて、日本は急速な近代化により、西洋の知識や技術が猛烈な勢いで流入しました。
この激動の時代に、西洋哲学の体系を取り込みながら、東洋、特に日本の伝統的な思想や禅仏教の概念を根底から見つめ直し、独自の哲学を打ち立てた人物がいます。
それが、西田幾多郎(1870-1945)です。
西田は、「京都学派」と呼ばれる日本の哲学潮流の創始者であり、彼が探求した「無の思想」は、単なる虚無や欠如ではなく、存在の根源を捉える深い概念です。
今回は、西田幾多郎の思想がいかにして西洋哲学と東洋の知恵を融合させたのか、そして彼が到達した「無の思想」の核心に迫ります。
ストリートアカデミーとは?
ストリートアカデミーは「もっと哲学のことを知りたい」や「茶道や陶芸など新しい経験をしたい」という人たちにぴったりの講座がたくさんあります。
様々な体験をして、新しい自分になるための一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか?
西田幾多郎の哲学への道:東洋と西洋の狭間で
西田幾多郎の人生は、まさに東洋と西洋の思想が交錯する場でした。
彼は、当時流入していたデカルト、カント、ヘーゲル、そしてベルクソンといった人物の主要な西洋哲学を深く学びました。
しかし、同時に彼は禅仏教の実践者でもありました。
特に、鈴木大拙(すずき だいせつ)との交流や、厳しい禅の修行は、彼の思想形成に決定的な影響を与えます。
当時の日本の思想界は、西洋の論理的な思考体系をいかに日本に取り込むか、という問題を抱えていました。
また、日本の従来の思想の脆弱性に直面してもいました。
この状況に対し、西田は単に西洋の理論を輸入するのではなく、禅の体験を通じて得た「無」を哲学的な概念へと昇華させる道を選びました。
西田の初期の代表作である『善の研究』(1911年)は、その試みの第一歩となりました。
西洋哲学との対話:「純粋経験」の提唱
西洋哲学は伝統的に、主体(私)と客体(世界)を対立的に捉え、その間に認識のギャップを想定してきました。
例えば、西洋哲学には「心身(物心)二元論」というものがあります。
まず主体(私、精神)があって、客体(世界、物、身体)を認識するという考え方です。
しかし、西田はこうした主客の分離以前の、より根源的な意識の状態に注目します。
それが「純粋経験」です。
皆さんは、何か芸術鑑賞をされている際に、自分と客体(鑑賞している物)が一体になっているような感覚を覚えたことはありませんか?
没入している感覚やぼぉーと何かをとらえている感覚に近いと思います。
西田幾多郎はそのような経験を「純粋経験」と呼びました。
つまり、「純粋経験」とは、物事を認識しようとする意識の働きが起こる以前、あるいは意識と対象が一体となっている状態を指します。
例えば、美しい花を見て「美しい」と感じる瞬間、思考が入り込む前にただ「美」そのものが感覚として直接的に現れている状態です。
私たちは、「純粋経験」(美しいものをただ見ている状態で、まだ美しいと「認識していない・思っていない状態」)をまず経験し、
その後に「主体が客体を認識する(この対象は「美しい」と認識する)というプロセスを経ていると西田は考えました。
この純粋経験の段階では、主体と客体の区別はなく、認識する主体も、認識される対象も、一つの連続した流れの中にあります。
西田は、この「純粋経験」こそが、人間の根源的な経験であり、かつすべての知識や存在の基盤であると考えました。
これは西洋哲学の枠組みの中で、禅の「悟り」や「無心」といった体験を説明しようとする試みであり、西田が東洋思想を哲学的に言語化する最初の試みでした。
「無の思想」の核心:「場所の論理」とは?
西田幾多郎の思想が最も独自性を発揮し、東洋と西洋の融合を深く実現したのが、「場所の論理」です。
私たちが普段「場所」と言うとき、それは「ここ」とか「教室」とか、具体的な空間を指しますよね。
しかし、西田幾多郎が考えた「場所の論理」の「場所」は、私たちが普段考えているような、ただの物理的な空間ではありません。
これは、「すべてが存在するための、一番根本にある『入れ物』」のようなものです。
この「場所」がなぜ重要なのかを理解するために、哲学的な考え方と、私たちの身の回りにあるものを比べてみましょう。
1. なぜ「場所」が大切なの?
私たちは「もの」や「人」といった「あるもの(有)」に注目しがちです。
- 「ここに本がある」
- 「あそこに先生がいる」
でも、西田は「それらがあるのは、一体どこか?」と考えました。
「ある」ためには、それを受け入れる「場所」が必要ではないでしょうか?
デカルトのような西洋の哲学は、「私(自己)」や「もの(実体)」といった「有」から考えをスタートします。
しかし、西田幾多郎は、その「有」が存在するためには、「無」(何もないこと)を基盤とする「場所」が必要だと考えたのです。
2. 「無」の「場所」ってどういうこと?
西田幾多郎の考える「場所」の最も難しい、そして最も大切なポイントは、その「場所」が「絶対無(ぜったいむ)」だということです。
「無」と聞くと、何もなくて空っぽな状態を想像するかもしれません。
しかし、西田の「絶対無」は、単なる空っぽではありません。
これは、「それ自体は何も持たないけれど、すべてのものを受け入れることができる場所」なのです。
例えば、皆さんが映画を見るときを想像してみてください。
- 映画のスクリーン自体は、映画が始まる前はただの白い布(無)です。
- しかし、映画が始まると、そのスクリーンに、登場人物や風景、ストーリーといった「有」(存在するもの)が映し出されます。
もしスクリーンがなかったら、映画は映し出せませんよね。
スクリーンはそれ自体は「無」ですが、映画という「有」を可能にしている「場所」なのです。
西田幾多郎の「場所」は、この「スクリーン」と同じように、私たちが住む世界や、私自身といった「有」を映し出す、根源的な「無」の場なのです。
3. 「場所の論理」が教えてくれること
「場所の論理」は、私たちの存在について、次のようなことを教えてくれます。
① 「ある」と「ない」は一つ
私たちが「ある」のは、「ない」(無の場所)があるからです。「有」と「無」は、対立しているようでいて、実は深く結びついています。私たちは、この「無」の場所の中で生き、活動しています。
② 世界はつながっている
「場所」は、私たちが独立して存在しているのではなく、すべてがこの「場所」の中で相互に関係し合っていることを示します。
私たちは個々の存在ですが、同時に、その存在は「場所」という全体と結びついています。
西田幾多郎は、この矛盾した状態を「絶対矛盾的自己同一(ぜったいむじゅんてきじこどういつ)」と呼び、それが世界のあり方だと考えました。
この概念によって、西田は「存在」が「無」の中でこそ成立するという、東洋的な世界観を論理的に表現しようと試みました。
「絶対矛盾的自己同一」:矛盾を生きる存在
西田哲学の最も難解であり、かつ重要な概念が「絶対矛盾的自己同一(ぜったいむじゅんてきじこどういつ)」です。
これは、西洋哲学がしばしば「矛盾律」(AはAであり、非Aではない)に基づいて論理を展開してきたのに対し、西田が東洋的な非二元論(二元論を超えた考え方)を取り入れた概念です。
「絶対矛盾的自己同一」は、相反するものが対立しながらも、根源的な「無」の場所において、そのまま一つになっている状態を指します。
例えば、「私」という個と、「世界」という全体は、対立しているように思えますが、お互いが存在するためには必要です。
すなわち、この二つは根源的な「絶対無」の場所においては一つなのです。
これは、私たちが生きる現実世界において、対立(個と全体、善と悪、生と死)が避けられないものでありながら、それらが最終的に一つの全体性の中で調和しているという、深い洞察に基づいています。
西田は、この矛盾をそのまま受け入れ、それを生きることこそが、真実の生であると考えました。
まとめ
西田幾多郎の「無の思想」は、彼の死後も、多くの思想家や哲学者、芸術家たちに影響を与え続けています。
現代社会は、科学技術の発展やグローバル化によって、物質的な「有」に偏重し、複雑な関係性の中で生きる私たちの存在を単なる「機能」や「機械」として捉えがちです。
しかし、西田の「無の思想」は、私たちが個としての存在を超え、他者や自然、そして世界の根源的な「場」と深く結びついていることを再認識させてくれます。
彼の哲学は、西洋の論理的な厳密さを保ちながら、東洋の深い洞察力、特に禅の精神性を融合させた、類まれな試みでした。
西田幾多郎が探求した「無」は、単なる概念的な空虚ではなく、私たちの存在と世界の根源を支える、満ち足りた「場」でした。
この「無」に立ち返ることこそが、現代社会が直面する多くの問題に対し、新たな視点と調和をもたらす鍵となるのかもしれません。
(参考文献)
・『善の研究(岩波文庫)』(著者:西田幾多郎)
・『西田幾多郎の思想 (講談社学術文庫)』(著者:小坂 国継)
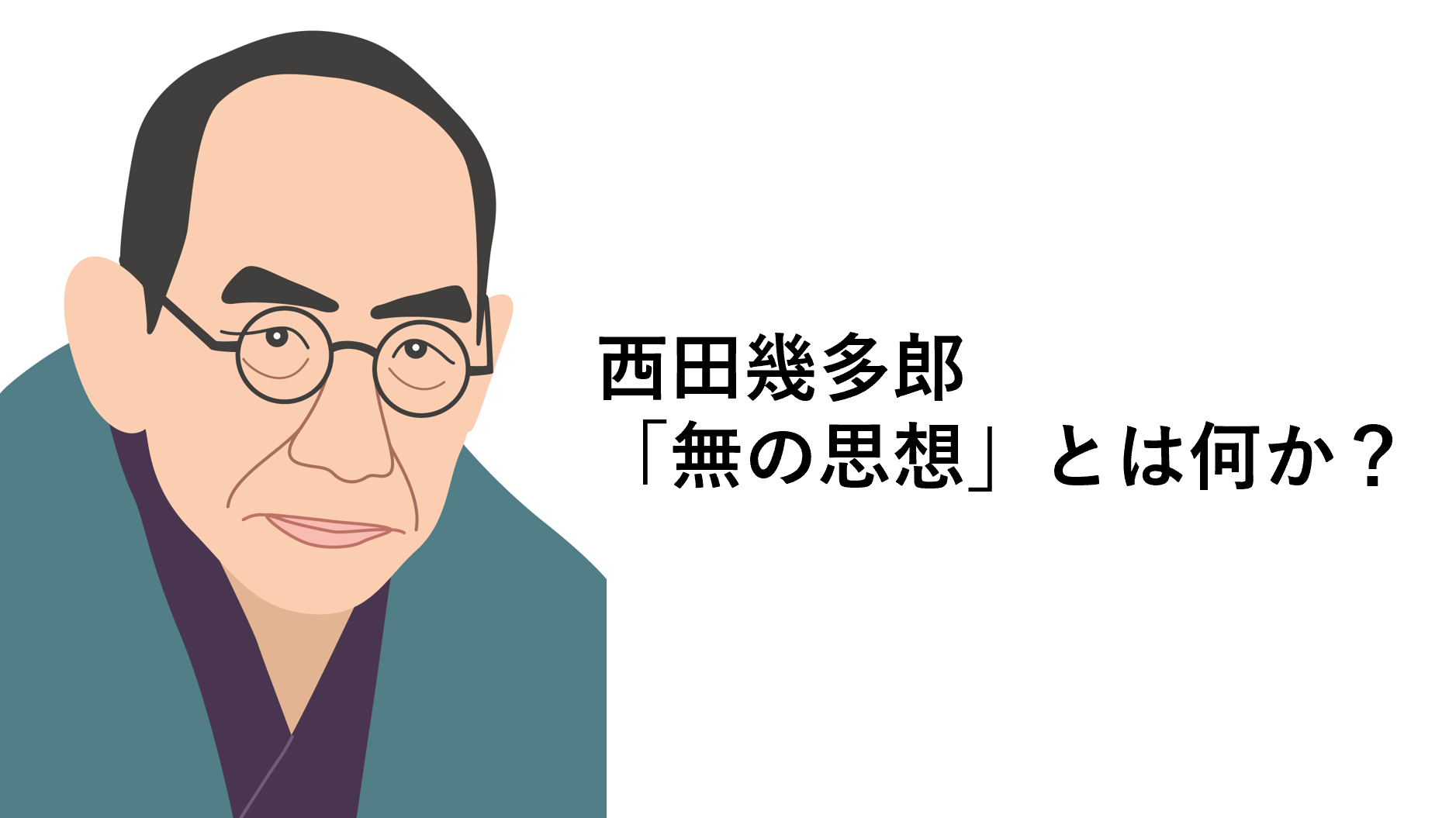
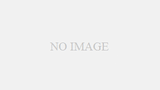

コメント