私たちの身の回りには、海外から入ってきた新しい文化や考え方がたくさんあります。
しかし、実は私たちが普段当たり前だと思っていることの中にも、昔から日本に伝わる独特の考え方や価値観が息づいています。
今回は、そんな「伝統的な日本の精神」について、わかりやすく、いくつかのキーワードを使いながら探っていきます。
少し難しそうに感じるかもしれませんが、きっと皆さんの日常生活にもつながる発見があるはずです。
ストリートアカデミーとは?
ストリートアカデミーは「もっと哲学のことを知りたい」や「茶道や陶芸など新しい経験をしたい」という人たちにぴったりの講座がたくさんあります。
様々な体験をして、新しい自分になるための一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか?
自然とともに生きる心 ~八百万(やおよろず)の神とアニミズム~
皆さんは、お正月に初詣に行ったり、お祭りで地域の神社にお参りしたりしますか?
神社に行くと、大きな木や岩にもしめ縄が巻かれていたりしますよね。
これは、日本人にとって自然が特別な存在だからなんです。
昔から日本には、「八百万(やおよろず)の神」という考え方があります。
これは、世の中のあらゆるものに神様が宿っている、という考え方です。
山や川、森、岩、風、雷、さらには私たちの暮らしを支える道具にまで、神様がいると信じられてきました。
この考え方は、「アニミズム」と呼ばれる、すべてのものに魂や霊が宿るとする原始的な信仰に近いものです。
西洋では、神様は人間とは別の、超越した存在として捉えられることが多いですが、
日本では神様は私たちの身近な自然の中にいる、と感じられてきました。
自然を畏れ敬い、感謝する気持ちは、私たちの生活にも深く根付いています。
例えば、食べ物をいただくときに「いただきます」と言うのは、命をいただくことへの感謝の気持ちです。
また、お墓参りをしたりするのも、モノに宿る魂を大切にする、という感覚に近いかもしれません。
その他、お守りをもったり、お札(ふだ)を大切にしたりと、日本人はアニミズム信仰を受け入れいる場面が多々あります。
この「自然とともに生きる心」は、日本独自の美しい風景や、環境を大切にする精神の根底にあると言えるでしょう。
調和を重んじる心 ~和の精神と「察する」文化~
日本人は、「和の精神」を大切にしてきました。
これは、みんなで仲良く、協力し合って、争いごとを避けようとする考え方です。
学校のクラスで何かを決めるときや、企業内でチームワークを意識するときに、自然とこの「和」の精神が働いているのを感じたことはありませんか?
特に日本は個を大切にするよりも共同体を大切にしてきました。
詳しくは次の記事をご覧ください。
この「和」の精神を支えるのが、「察する」という日本のコミュニケーション文化です。
相手の言葉の裏にある本当の気持ちや、場の空気を読み取って行動する。
これは、直接的な意見の衝突を避けて、円滑な人間関係を築くための知恵でもあります。
例えば、友達が困っていそうなとき、言葉に出さなくても「どうしたの?」と声をかけたり、手伝ったりすることがあります。
これは、相手の様子から気持ちを「察して」行動しているといえます
もちろん、何でもかんでも「察して」ばかりいると、自分の意見が言えなくなってしまうこともあります。
最近では、もっとはっきりと自分の意見を伝えることが大切だ、という考え方も広まってきています。
でも、相手を思いやり、調和を大切にする「和」の精神は、多様な価値観を持つ人々が共に生きていく現代において、改めて見直されるべき大切な心だと思います。
簡素さを愛する心 ~「わび・さび」~🌿
日本の伝統的な文化には、豪華さや華やかさよりも、「簡素さ」や「素朴さ」を美しいと感じる独特の美意識があります。
それが、「わび・さび」に代表されるものです。
「わび・さび」は、言葉で説明するのが少し難しい概念ですが、簡単に言うと、
- わび: 静けさや落ち着きの中に見出す美しさ。質素で簡素なものの中に豊かさを感じる心。
- さび: 古びたものや、時間の流れを感じさせるものの中に宿る美しさ。朽ちゆくもののはかなさや、無常観を感じる心。
といった意味合いがあります。
例えば、苔むした庭園や、使い込まれた道具、シンプルだけど洗練されたデザインのものなどに、この「わび・さび」の精神を見ることができます。
例えば、「満月」より「欠けた月」が、「満開の花」より「枯れていく葉っぱ」が良かったりする精神性です。
「わび」と「さび」は、元々は別の概念でしたが、茶道や俳諧などを通じて結びつき、「侘び寂び」として日本文化を代表する美意識として定着しました。
この美意識は、日本庭園、茶室、陶芸、絵画など、日本の様々な文化に影響を与えています
そして、「侘び寂び」は、単なる美意識だけでなく、人生観や価値観にも影響を与える深い概念です。
不完全なもの、変化していくものを受け入れ、そこから得られる静けさや安らぎを大切にする、日本ならではの美意識と言えるでしょう
変化を受け入れる心 ~「無常観」と「諸行無常」~
日本の精神には、「無常観(むじょうかん)」という考え方も深く根付いています。
これは、この世の全てのものは常に移り変わり、同じ状態にとどまることはない、という仏教の教え「諸行無常(しょぎょうむじょう)」に基づいています。
桜が満開に咲き誇り、やがて散っていく様子など、あらゆるものに終わりがあり、変化し続けることを受け入れる心です。
一見すると寂しく感じるかもしれませんが、
この無常観は、新しい変化を恐れずに受け入れる柔軟な心を育むとともに、、今この瞬間を大切に生きる気持ちを重要視することにもつながりました。
もしかしたら、明治維新の際に西洋化したのも、多彩な宗教的文化を受け入れることができたのも、この柔軟性があったからかもしれません。
まとめ:伝統的な日本の精神は、私たちの未来を照らす光 ✨
ここまで、「伝統的な日本の精神」について、いくつかキーワードを挙げながら見てきました。
- 自然とともに生きる心(八百万の神、アニミズム)
- 調和を重んじる心(和の精神、察する文化)
- 簡素さを愛する心(わび・さび)
- 変化を受け入れる心(無常観、諸行無常)
これらの精神は、私たちが日々の生活の中で意識することは少ないかもしれません。
しかし、ふとした時にこれらの精神性に気づくときがあるかもしれません。
伝統的な日本の精神は、過去のものなく、現代においても生き続けいます。
ぜひ、皆さんも身の回りにある日本の文化や習慣の中に、今回紹介したような精神が息づいていることを感じてみてください。
それが、自分たちのルーツを知り、未来を考えるきっかけになるかもしれませんよ。
最後までありがとうございました。



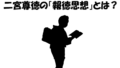
コメント