今回は、公共空間について、哲学者の意見を踏まえて解説します。
新教科の公共の教科書の最初には、「公共空間」の説明が続きます。
正直、「抽象的で意味不明だな」、と思われる人も多いと思います。
私なりに「公共空間」に関する点を簡潔にまとめましたので、ぜひ参考にしてください。
ストリートアカデミーとは?
ストリートアカデミーでは、大人の学びなおし、子どもの学習のために様々な講座をお手頃価格で受けられます。
「もっと歴史や哲学のことを知りたい」や「茶道や陶芸など新しい経験をしたい」という人たちにぴったりの講座がたくさんあります。
様々な体験をして、新しい自分になるための一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか?
公共空間:「自由」と「正義」が交わる場所(ロールズ)
公共空間とは、公園、広場、道路、図書館、駅、学校など、誰もが自由に使ったり出入りしたりできる場所のことです。
これらの場所は、私たちの毎日の生活の中で、偶然の出会いや、目的のある交流を生み出す大切な場所になります。
私たちが公共の場にいるとき、そこにはいつも「自由」と「ルール(正義)」という2つの考え方が関係してきます。
自由と正義
自由とは、公共の場で私たちがどう行動し、何ができるかということです。
公園で散歩したり、本を読んだり、友達とおしゃべりしたり、デモに参加したりと、私たちは様々な形で自分を表現し、活動することができます。
この自由は、一人ひとりの大切な気持ちを守り、色々な考え方が共存する社会を作るために必要不可欠です。
しかし、自由には限界があります。
「どこまで自由にしてもいいの?」という問題に深く関わってくるのが、ルール(正義)という考え方です。
公共の場では、色々な人がそれぞれの「自由」を使おうとします。
ある人の自由な行動が、他の人の自由や権利を邪魔してしまうこともあります。
例えば、大音量で音楽を流す自由は、静かに過ごしたい人の自由を妨げるかもしれません。
デモをする自由は、通りたい人の邪魔になるかもしれません。
ここで必要になるのが、みんなで守るべきルールや基準、つまり「ルール(正義)」の視点です。
ルール(正義)とは、一人ひとりの自由を尊重しながら、社会全体がうまくまとまり、秩序を保つための考え方と言えます。
正義に関して詳しく知りたい方は以下の記事も参考にしてください。
哲学者のジョン・ロールズが言った「正義の二原理」は、公共空間における正義を考える上で重要な視点を提供します。
一つ目は、「各人は、他者の同様な自由と両立しうる限りで、最も広範な基本的自由への平等な権利をもつべきである」
つまり、「すべての人が他の人と同じように、最大限の自由を持つべきだ」という考え方です。
これは、公共の場での一人ひとりの自由を守ることを意味し、ロールズはこの原理はどんな原理・原則よりも優先されるものだと説きました。
二つ目は、「社会的・経済的不平等は、(a)最も不遇な人々の利益になるように配置され、かつ、(b)公正な機会の均等という条件のもとで、すべての人々に開かれた職務や地位に付随するものでなければならない」
すなわち「社会や経済の不平等がある場合、それは一番困っている人のためになるように、そしてみんなに平等なチャンスが与えられた上で、誰でも同じように目指せるような地位や仕事につくべきだ」という考え方です。
これは、公共の場がみんなに公平に使えるように、社会的に弱い立場の人にも配慮することを求める考え方です。
公共の場でルール(正義)を実現するのは、時に難しいことです。
例えば、公園で寝泊まりするホームレスの人の権利と、公園を気持ちよく使いたい一般の人の権利は、ぶつかることがあります。
また、表現の自由を主張するデモと、それが嫌だと感じる人の気持ちも、ぶつかることがあります。
このような対立を乗り越えて、より多くの人が公平で居心地の良い公共の場を作るためには、どのようなことをするべきでしょうか。
それは「対話」です。
公共の場での「対話」が未来を作る(ハーバーマス・アーレント)
私たちがより良い公共空間を築いていく上で、最も重要と言えるのが「対話」です。
公共の場には、様々な考え方や背景を持つ人が集まります。
だからこそ、意見のぶつかり合いが生まれることも少なくありません。
しかし、その意見のぶつかり合いを避けるのではなく、お互いの話に耳を傾け、なぜそう考えるのかを理解しようとすることが、真の「公共性」を育む上で不可欠なのです。
ハーバーマス・アーレントと「対話」の関係
哲学者のハーバーマスはどんな人間にも「対話的理性」が備わっていると説きました。
これは、対話によって解決策を導くことのできる能力のことです。
ハーバーマスはヒトラー政権を誕生させたのは、対話をおろそかにしたからだと分析し、
きちんと対話を重ねれば、ヒトラーを生んだドイツのような独裁国家にはならないはずだと説明しています。
また、哲学者のハンナ・アーレントも同様に人間はコミュニケーションをすべき(=「活動」をすべき)と説いています。
アーレントの主張の背景にはドイツのホロコーストにおける責任者の裁判(アイヒマン裁判)が関係しています。
彼は裁判でユダヤ人のことを虐殺したことを「悪いと思っているか」と聞かれたときに
「上からの指示を受けただけで、悪気が無かった」と言いました。
アーレントはこれを聞いて、大変ショックを受けたと同時に誰でもその責任者のようになりかねないとも思いました。
それは、上からの指示待ち人間は自ら思考することを放棄し、自律していないからです。
アーレントは、だからこそ、コミュニケーションを取って自分の行いが正しいかなどを議論すべきなのだと主張しました。
公共空間と対話
対話は、単に自分の意見を主張するだけでなく、相手の立場に立って考え、共感しようとすること、
そして共通の課題を解決するために共に知恵を出し合うことです。
たとえ意見が異なっても、対話を通じて互いの多様性を認め合い、理解を深めることができます。
例えば、公園で新しい遊具を設置する際、子どもを持つ親と高齢者、あるいは近くに住む住民とでは、それぞれ異なる要望があるかもしれません。
そうした時に、一方的に決めるのではなく、話し合いの場を設け、それぞれの意見を聞き、何が一番みんなにとって良い方法なのかを共に考える。
これが、公共空間における対話の力です。
対話の機会が失われると、社会は分断され、互いを理解しようとする姿勢が失われてしまいます。
それは、公共の場が持つ「みんなで共有する場所」としての機能を失わせることにもつながりかねません。
だからこそ、私たちは、日々の生活の中で、小さなことからでも対話を意識し、実践していく必要があります。
物理的な公共空間でも、インターネット上の仮想空間でも、互いに向き合い、話し合い、理解を深めること。
これこそが、私たちが一人ではない社会で、より良い未来を共に作っていくための確かな道です。
公共空間は、ただ存在するだけでなく、私たちの対話によってその価値を最大限に発揮できる場所なのですから。
まとめ
私たちは一人では生きていけません。
人々とつながる公共空間では、個人の自由と社会のルール(正義)が常に大切になります。
そこには多様な人々がいるため、意見の対立が生まれることもあります。
だからこそ、お互いを理解し、より良い社会を築くためには、対話が不可欠なのです。
以上がご覧いただきありがとうございました。
参考文献は以下になります。
ぜひご覧ください。
・『正義とは何か』(神島裕子 著)
・『倫理学入門 アリストテレスから生殖技術、AIまで』(品川哲彦 著)
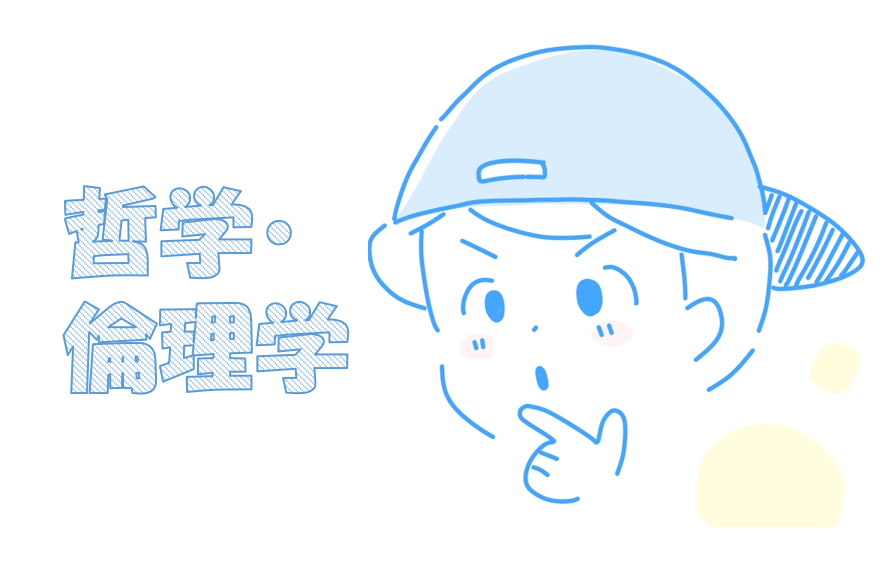



コメント