皆さんこんにちは。よっとんです。
哲学倫理・歴史・心理、それから本紹介のブログを書いています!
本日は、福沢諭吉を忘れるなプロジェクト第3弾!
「『学問のすすめ』はなぜ大ベストセラーに?」をお届けします!
実は、諭吉の『学問のすゝめ』は約350万部の大ベストセラーになりました。
これは、当時の人口からすると、10人に1人は読んでいたことになります!すごい!
なぜ、これだけ読まれたのでしょうか??
今日は『学問のすすめ』がどんな内容なのかを含め、大ベストセラーの秘密に迫りたいと思います!
まだ、福沢諭吉を忘れるなプロジェクト第1、2弾をお読みでない方はそちらもどうぞ
『学問のすすめ』は国民を「啓蒙」するため?

『学問のすすめ』はいわゆる啓蒙思想の一種です。
啓蒙とは「蒙昧を啓く」こと、
蒙昧は無知、暗い様子を意味します。啓くは光が射しこむ感じです。
「無知の状態」から「知の状態」へもっていくのが啓蒙思想です。
日本では明六社という啓蒙思想団体が有名です。
詳しくは下の創設者の森有礼をご覧ください。
福沢諭吉は明六社のメンバーでした。
彼がしたことは、江戸から明治になった後、
外面だけ変わったが心が追い付かない日本人、また今までの悪習がなかなかぬぐえない日本人などに、
新たな生き方を明示することでした。
そこで『学問のすすめ』を執筆し、日本人に新たな希望と勇気を与えたのです。
では、実際に中身を見ていきましょう!
全ての人は平等だと自覚せよ!

『学問のすすめ』の最初の文章は皆さんもご存じでしょう。
「「天は人の上に人を造らず、人の下に人を造らず」といへり」
これは天賦人権思想を説いたものです。
天賦人権思想とは天から基本的な人権は与えられているものだ、という考え方のことです。
簡単に言えば、生まれつき人は平等ということです。
ただ、諭吉はだからといって自由奔放に生きていいと言っているわけではありません。
ここでの平等とは、現実のあり方ではなく、権利上の平等です。
どういうことか?
現実には、貧富・強弱といった差はあります。だから現実のあり方は平等とはいえません。
しかし、人がこの世に生まれたのは、人の力ではなく、天によります。
天は人に心と身体を平等に与えました。
百姓が甘いと感じるものは、地頭にも甘い、百姓が痛いと感じるものは、地頭も痛いのです。
そして、この心・身体に基本的人権を与えたのです。
だから、人類は皆、権利の上では平等なのです。
現代の私たちが聞けば当然の主張なのですが、当時は明治がはじまったばかりです。
四民平等になったとはいえ、未だに身分制の風習・意識が排除しきれていない時期でした。
そんな時代に諭吉は、貧しい人も、お金のある人も、偉い人も、商売人も、
全ての人は権利の上では平等なんだ、と説いたのです。
だから、恐れる必要はない、
もし人権を侵害してくる人がいれば、それが政府だろうが、西洋諸国だろうが、
全力で立ち向かっていいのだ!
諭吉は以上のように述べて、国民たちを勇気つけたのでした。
一身独立して、一国独立す

次に、『学問のすすめ』において、最も主張しているともいえるもの、
「一身の独立」についてお話しします。
諭吉は、「1人1人が独立することで、国が強くなる」という考えを持っていました。
ここでいう独立とは、「自分で自分の身を支配し、他に依存する心がない状態」です。
自分自身で物事の正しい・正しくないを判断したり、頭や体を使って生計を立てているものは、他に依存していないといえます。
例えば、流行によって服を変える人がいますが、
自分の意志より「流行」に縛られているのならば、それは独立できているとは言えません
「流行」だからではなく、自分の意志で服を決める、そうした時初めて「独立した」と言えるということになります。
今のは簡単な例でしたが、自分の意志で判断するということ自体はなかなか難しいです。
進学先、就職先など、偏差値、年収、知名度など他人の意見によらずに自分で決めるというのは結構大変ですよね・・・
ただ、諭吉は当時の日本人に「一身独立」することが一国を独立させる(西洋と対等の地位に上り詰める)ために必要だと説いたのです。
その理由は、一つには独立の気概がないと、国を思う気持ちもなくなるからというものです。
自分でなんとかしようと思わなくなると、国(政府)のお客さんのような人物になります。
政府の命令通りに生きるだけで、意見をいうこともない。
これは国内だけのことならいいのですが、
外国と戦争となったときなんかは、主体的に行動できない人間はかえって邪魔になる。
外国に対して自国を守ろうとするなら、独立心が必要なのです。
2つ目は独立した立場を持っていない人は、外国人と接するときも権理を主張することができない、からです。
独立していない商人は、外人の体格の大きさ、蒸気船のスピードなどに恐れをなし、
法外な値段を出されても、その値段で売買してしまいます。
これは商人一人の問題ではなく、いずれは国全体の問題となります。
明治の始まりの頃は、未だ国民の中に儒教的精神、即ち、偉い人に従順する心が抜けていませんでした。
制度上の身分はないにしろ、町人身分の人がお偉いさんにへりくだる姿勢や気風が抜けません。
諭吉はむしろお偉いさん(政府・官僚)ではなく、
国民(民間)が事業を始めたりして手本を見せていくことが重要だと説きます。
「世の中の事業は、ただ政府のみの仕事ではない。学者は学者として、官に頼らず事業をなすべし。町人は町人で、官に頼らず事業をなすべし。政府も日本の政府であり、国民も日本の国民である。政府を恐れてはいけない、近づいていくべきである。政府を疑うのではなく、親しんでいかなければならない」という趣旨を知らしめれば、国民もようやく向かっていくところがはっきりし、上がいばり、下は卑屈になるという気風も次第に消滅して、初めて本当の日本国民が生まれるだろう。
『現代語訳版 学問のすすめ』福沢 諭吉著 齋藤 孝訳
こうすることで、政府への刺激にもなります。結果的に日本全体が強くなる。
だから、一身が独立することが大事なのです。
では次に、一身独立をするために具体的に何をするべきなのか、についてお話しします!
※諭吉は「官に頼るな」と言っているわけではなく、民間と政府がどちらも刺激し合う関係が重要と言っています。
勉学に励め!
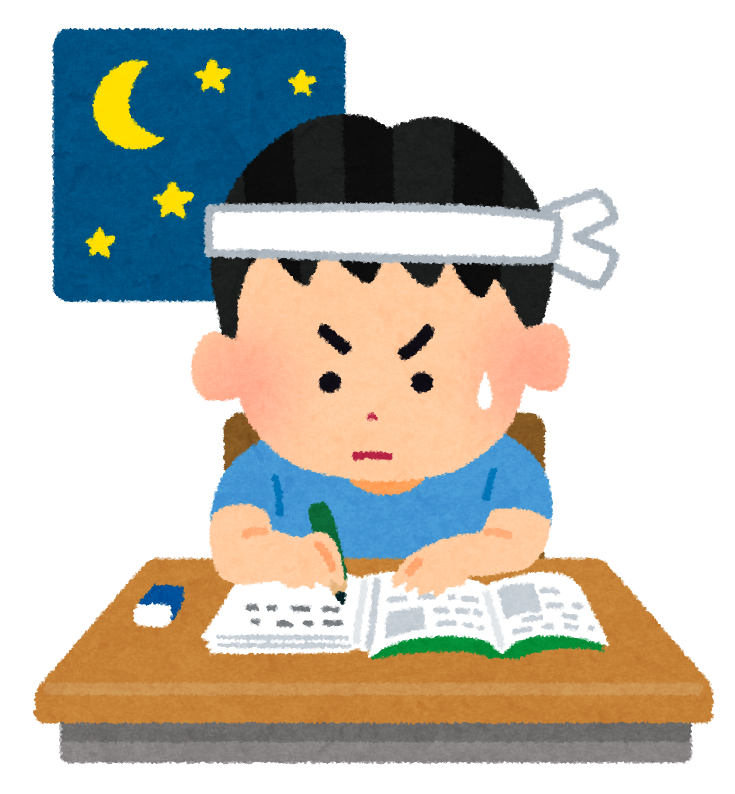
福沢諭吉の主な主張は「一身独立することで一国独立させる」ことです。
愚かな民が賢くなり、政府と調和した状態になることが目標です(これを官民調和といいます)
そのために国民一人一人が取り組むべきこととして諭吉があげているのは、
勉学です。
ただ、学ぶべきものは何でもいいわけではありません。
諭吉が学ぶべきとしているのは、「実学」です。
実学とは、「人倫普通日用に近き実用的学問」のこと、
簡単にいえば、普段の人間関係(生活)で使える学問ということです。
具体的にいえば、
読み・書き・そろばん以外に、修身(倫理・道徳),宗教,哲学,天文,地理,物理,化学などです。
日本人は江戸期まで漢文や古文、和歌を学とすることが多かったのですが、
諭吉はそれらは実学ではないとしています。
「和歌がうまくて、商売ができるという人はあまりいない」といいます。
それよりも、西洋からの学問(洋学)を中心とした実学を学ぶべきとしています。
日常に役立つ実学は、逆を言えば日常生活からも学ぶことができるものです。
家計簿をつけること、世の中で何が売れているか察知して商売することは全て経済です。
そういう身近なところから学問にははげむことも大事なのです。
そして、国民は学問に励んでいくうちに、物事の筋道が見えてくるようになります。
これは世界がどうなっているかを学ぶことができるということです。
すると、自分が今何をすべきかがわかってきます。
つまり、自分の社会的役割を知ることができるのです。
これが諭吉が「勉学→一身独立」に繋げている理由です。
勉学をすると、自分の社会的役割を果たすようになり、結果的に国の総力があがる、
だから、諭吉は勉学に励むことを国民に説きました。
まとめ
『学問のすすめ』はいかがでしょうか。
福沢諭吉が『学問のすすめ』で一番いいたかったのは「一身独立して一国独立す」でしょう。
国民それぞれが勉学に励み、他人に依存しなくなれば国民全体のレベルがupします。
すると、国家の総力がupして、日本という国が世界を渡り合えるようになるのです。
この『学問のすすめ』が当時ベストセラーになった理由は、
おそらく国民に今やるべきことを自覚させ、自信を持たせたからだと思います。
明治の初め、文明開化で色々な技術が入ってきて、確かに華やかにはなりました。
しかし、国民が戸惑います。
「これからどうやって生きていけば・・・」
そんなときに彼は一つの道筋を提示してみせたのです。
『学問のすすめ』には、他にも・・・
今やるべきことがわからない
自分の考えを堂々と主張したい
自由とわがままの違いとは?
などとても役に立つものがたくさん載っています。
そして(諭吉自身が自分で言っているのですが)、何より読みやすい!
その読みやすいのを、齋藤孝さんはさらに読みやすく現代語訳してくれました!
ぜひ皆さんも学問のすすめを読んでみてはいかがでしょうか?
ここまでご覧いただきありがとうございました!
参考文献を載せておきます!
☆『学問のすすめ 現代語訳版』(ちくま新書)翻訳:斉藤 孝
☆『福翁自伝 現代語訳版』(ちくま新書)翻訳:斎藤 孝
☆『人と思想 21福沢諭吉』(清水書院)著者:鹿野 政直
☆『福沢諭吉が見た150年前の世界 『西洋旅案内』初の現代語訳』(彩図社)翻訳:武田 知弘
☆『西洋事情』(慶應義塾大学出版会 )編集: マリオン・ソシエ, 西川 俊作
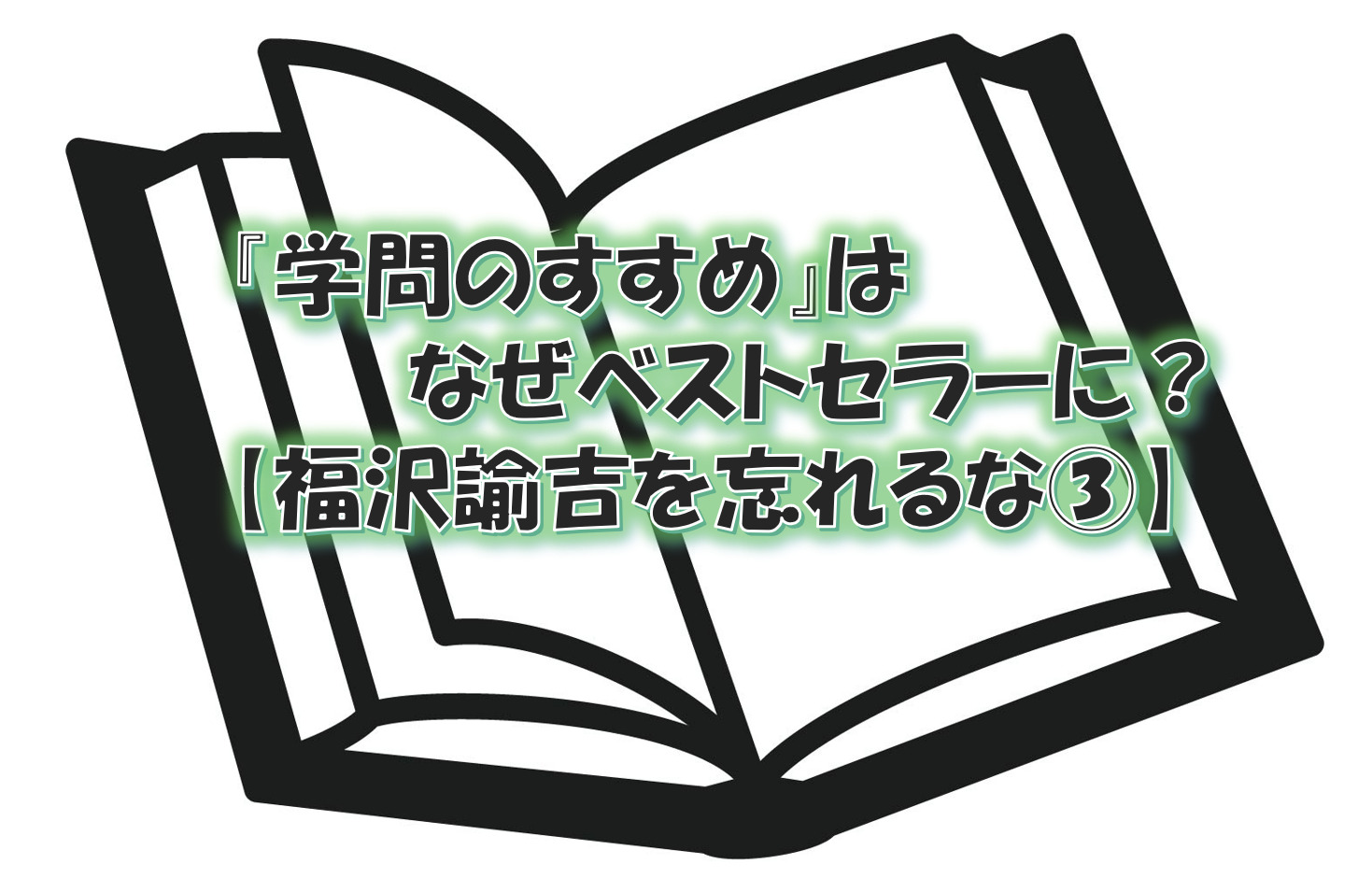

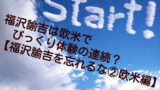



コメント