本日は、「西洋哲学と東洋哲学での「愛」をまとめてみた」というテーマで書きます。
「愛」と聞くと皆さんは何を思い浮かべるでしょうか?
ほとんどの人は恋愛ですかね?
しかし、愛にも色々な意味があります。
今回は西洋と東洋の哲学思想(宗教)を取り上げて、「愛」についてまとめてみました。
ぜひ最後までご覧ください。
ストリートアカデミーとは?
ストリートアカデミーでは、大人の学びなおし、子どもの学習のために様々な講座をお手頃価格で受けられます。
「もっと歴史や哲学のことを知りたい」や「茶道や陶芸など新しい経験をしたい」という人たちにぴったりの講座がたくさんあります。
様々な体験をして、新しい自分になるための一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか?
西洋哲学の愛
まずは、西洋哲学での愛シリーズを見ていきましょう。
ギリシア語で愛は三つの言葉で言い表されます。
今回は、その3つをご紹介しましょう。
エロース
一つ目は「エロース」です。
「エロい」という言葉の語源にもなっています。
エロースは、ギリシア語で「一方的な愛」という意味です。
元々は「見えないものへの憧れ」という意味を持っていました
見えないものへの憧れという概念が、
やがて相手の身体の見えない部分を想像する「エロティック」という言葉につながっていったとされています(※諸説あり)。
このエロースは、古代ギリシアの哲学者プラトンのイデア論においても重要な概念として登場します。
プラトンのイデア論は、私たちが住む現実世界とは別に「イデア界」という完璧な世界が存在すると説きます。
イデアは「完全なもの」を意味し、物理的に存在するものではなく、概念的な存在です。
私たちの日常で使う「アイデア(idea)」という言葉の語源でもあります。
イデア界には、すべてのものが完全な形で存在しています。
プラトンは、私たちの魂は元々イデア界の住人であり、完璧なイデア界から現実世界に降りてきたと考えました。
現実世界は、イデア界にあるイデアの不完全な模倣品で構成されています。
そのため、私たちは本能的に、完璧なイデア界に対して一方的な憧れや愛を抱くのです。
プラトンはこのイデア界に対する一方的な愛を「エロース」と呼びました。
つまり、プラトンにとってのエロースは、単なる肉体的な欲望を超え、真・善・美といった究極的な完全性への魂の希求を意味するものでした。
フィリア
次に紹介するのは、同じくギリシア語の「フィリア」です。
この言葉は「相互の愛」や「双方向の愛」を意味します。
前回の「エロース」が一方的な片思いだとすれば、
フィリアはまさに「両想い」の状態を指すと言えるでしょう。
古代ギリシアの哲学者アリストテレスは、この「フィリア」こそが国家にとって最も重要な徳目であると主張しました。
なぜなら、すべての人がフィリアの心を持っていれば、社会は平和になるからです。
想像してみてください。
もし誰もが互いを愛し、助け合い、手を取り合って生活する社会が実現したら、
そこに過度な規制や法律は必要ないかもしれません。
それはまさに理想的な社会だと思いませんか?
フィリアがあれば、人間関係は極めて良好に保たれるはずです。
しかし、アリストテレスは同時に、すべての人がフィリアの徳を持つことの難しさも理解していました。
だからこそ彼は、次に重要となるものとして「正義の徳」を挙げ、
社会の秩序を保つために規制や法律を整備することの必要性を説いたのです。
アガペー
西洋における愛の概念の最後を飾るのは、「アガペー」です。
これもギリシア語に由来し、「無差別・無償の愛」を意味します。
無差別の愛とは文字通り、誰に対しても分け隔てなく愛すること。
そして無償の愛とは、一切の見返りを求めない愛のことです。
アガペーを説いた人物として最も有名なのが、イエス・キリストです。
キリスト教では、神が私たちにこの「無差別・無償の愛」を与えてくれると説かれています。
では、私たちはどのように応えるべきなのでしょうか? イエスは私たちに二つのことを求めました。
1. 神への愛(絶対愛)
一つ目は、神を愛することです。
これは「神への愛」、あるいは「絶対愛」とも呼ばれます。
神から惜しみない愛を受けているのだから、私たちもその愛に応えるのは自然なことです。
2. 隣人愛:出会うすべての人への愛
しかし、イエスの教えはここで終わりませんでした。
彼が万人に受け入れられた理由の一つは、この二つ目の教えにあります。
それは「隣人愛」です。
「隣人」とは、単にあなたのすぐ近くにいる人だけを指すのではありません。
あなたが出会うすべての人という意味も含まれています。
「今日出会った見知らぬ人にまで愛を?」と抵抗を感じる方もいるかもしれませんね。
ですが、この「愛」は、「抱き合ったりキスしたり」といった行動を求めているわけではありません。
この隣人愛の実践は、「黄金律」に基づいて行えば良いのです。
黄金律とは、「あなたがして欲しいことを、他人にもする」というものです。
例えば、誰かに挨拶されて気持ちが良いと感じるなら、あなたも自分から挨拶をすればいい。
そんな小さな行動一つ一つが、アガペーの実践につながるのです。
エロース、フィリア、そしてアガペー。西洋哲学における3つの愛の概念をご紹介しました。
それぞれの愛が持つ意味合いを比較すると分かりやすくなると思います。
東洋哲学の愛
これまでは西洋の愛の概念を見てきましたが、東洋の思想にも「愛」に通じる大切な教えがあります。
いくつかご紹介します。
儒家思想の「仁」
一つ目は、儒家思想における「仁」という徳目です。
「仁」は「親愛の情」という意味で、現代の言葉で言うと「思いやり」に当たります。
儒家思想の祖である孔子は、人間関係において最も重要な徳目としてこの「仁」を掲げました。
西洋思想との決定的な違い:「分」を前提とした人間関係
儒家思想の大きな特徴は、人間関係には「分(ぶん)」がある、
つまり「人には違いがある」ということを前提にしている点です。
西洋哲学が「人は生まれながらにして平等である」という考えから出発するのに対し、
儒家思想は「人間には生まれつきの差がある」という現実を認めるところから始まります。
考えてみれば、現実世界には力の強い人もいれば弱い人もいますし、お金持ちもいればそうでない人もいます。
足の速い人もいれば遅い人もいる。
こうした人々の違いを認めた上で、ではどうすれば人間関係を良好に保てるのか、
という人間関係論に焦点を当てているのが儒家思想なのです。
そのため、「仁」の内容も、基本的に上下関係のある人間関係を前提に説明されます。
「仁」の実践例:孝と悌
具体的な例を見てみましょう。
- 孝(こう) 「孝」は「親への愛」を意味し、親孝行のことです。子が親を敬い、愛することを示します。一方で、親が子を愛することは「孝」とは呼びません。
- 悌(てい) 「悌」は「年少者から年長者に対する愛」です。例えば、弟が兄を慕うことは「悌」に含まれますが、兄が弟を思いやることは「悌」ではありません。
このように、儒家思想における「仁」は、「世の中に上下関係が存在する」という前提の上で、
その中で円滑な人間関係を築くために実践されるべき思いやりなのです。
墨家思想:兼愛
西洋におけるイエス・キリストの「アガペー(無差別・無償の愛)」に似た概念が、東洋にも存在します。
それは、中国の思想家・墨子(ぼくし)が説いた「兼愛(けんあい)」です。
兼愛とは、「兼ねて愛する」、
つまり人々を広く、そして無差別に愛することを意味します。
厳密には「無償の愛」という点ではアガペーと少し異なりますが、その本質は非常に近いと言えるでしょう。
墨子が活躍したのは、戦乱が絶えなかった中国の春秋戦国時代。
そんな時代にあって、彼は徹底した絶対平和主義を貫きました。
残念ながら、彼の「兼愛」の思想を採用する国は当時一つも現れませんでしたが、
墨子の真にすごい点は、彼自身がその平和主義を徹底して実践したことです。
墨子は、自ら率先して他国を攻めることは決してしませんでした。
そして、もし攻め込まれるようなことがあれば、反撃するのではなく、
ひたすら守り抜く「籠城(ろうじょう)戦」を展開したのです。
このように、己の信念を貫き、身をもって平和を実践した墨子の生き様は、まさに「カッコいい」の一言に尽きます。
だからこそ、彼の思想は2000年以上経った今もなお、私たちに語りかけ続けているのかもしれませんね。
慈悲
西洋と東洋の様々な愛の形を見てきましたが、
最後に紹介するのは仏教における「慈悲」です。
慈悲の本来の意味は、「人々を哀れみ、苦痛を取り除くこと」。
ここでは、仏教の開祖であるブッダ(ゴータマ・シッダッタ)が説いた慈悲について見ていきましょう。
ブッダが説いた慈悲は、「生きとし生けるものすべてへの愛」というものでした。
この「生きとし生けるもの」という点が非常に重要で、人間だけでなく、動物を含むすべての生命が含まれるのです。
ブッダの有名な物語に、このような話があります。
彼がゴータマ・シッダッタとして生まれ変わる前、まだウサギだった頃のことです。
ある寒い日、空腹で倒れそうな聖者がいました。
二人は一緒に火にあたっていましたが、聖者は今にも力尽きそうでした。
その時、ウサギだったブッダがどうしたかというと、なんと自ら火の中に飛び込んだのです。
それは、聖者が自分を食べて生き延びられるようにという、究極の自己犠牲でした。
これは極端な例かもしれませんが、慈悲とはまさにこのような精神を指します。
すべての生きとし生けるものは繋がっているのだから、差別なく愛し合うべきだという教えが込められているのです。
ブッダがすべての生き物を平等に扱おうとした背景には、
彼が当時のインドにあった厳格な身分制度(ヴァルナ制、現在のカースト制)に強く反対していたことが理由だと考えられています。
あらゆる生命に分け隔てなく愛を注ぐこと、これこそがブッダの説いた「慈悲」でした。
まとめ
「愛」と一言にいっても色々なものがあるのですね。
日本の「愛」といったら恋愛のことを思い浮かべてしまう人がほとんどだと思います。
しかし、その考え自体も明治時代以降「恋愛」という概念が西洋からもたらされて以降の考え方でした。
そもそも日本には恋愛結婚なんてものはなかったのですから。
歴史を見てみると私たちが普通に思ってしまっていることが、普通ではないことを知ることができますね。
それが歴史・哲学を学ぶいいところかもしれません。
ここまでご覧いただきありがとうございました。
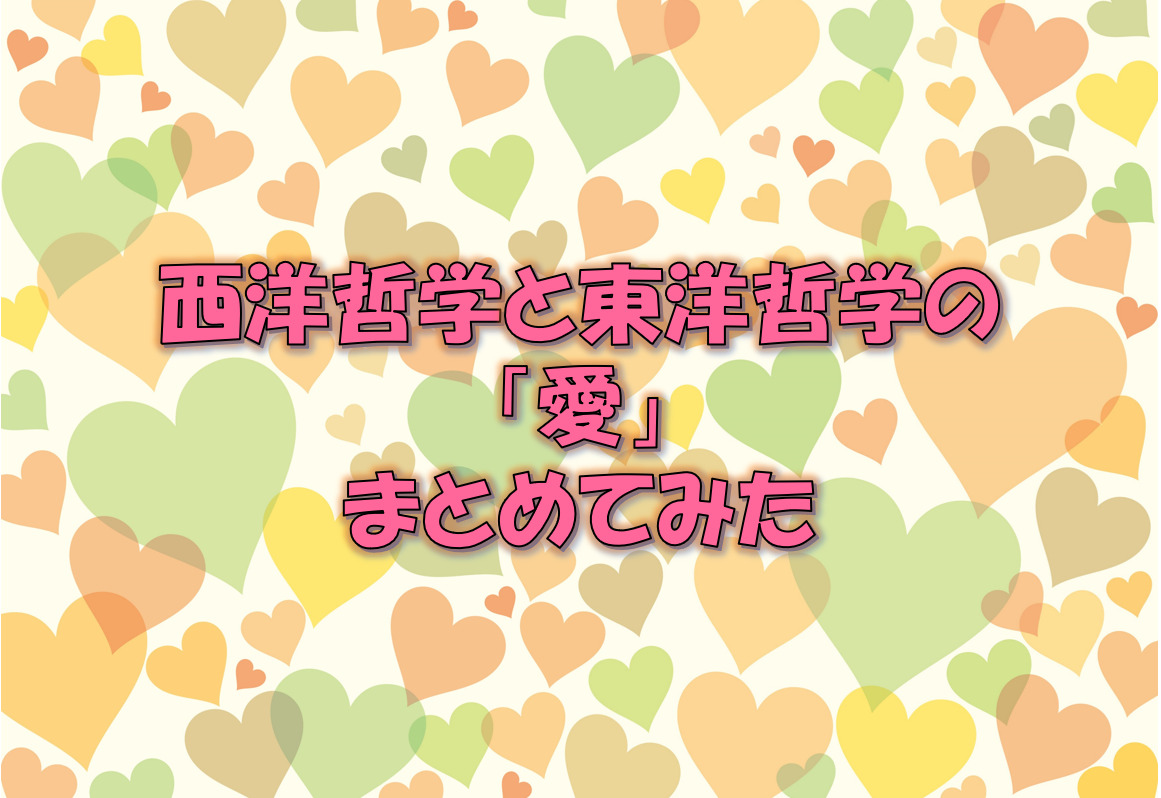


コメント