こんにちは、よっとんです。
哲学倫理・歴史・心理学、それから本紹介のブログを書いています。
本日は「西洋哲学史(ざっくりまとめ)」です。
とりあえず、西洋哲学の全体像を学びたい!という方に向けたものです。
今回は全体像なので、かなり細かい所は省きました。
あの人物がいない!ということもあると思いますが、
まずは「西洋哲学」がどのようなものなのか大まかに理解していただければなと思います。
哲学史を古代・中世・近代・現代に分けて書いています。
さて、では早速内容に入っていきましょう。
ストリートアカデミーとは?
ストリートアカデミーは「もっと哲学のことを知りたい」や「茶道や陶芸など新しい経験をしたい」という人たちにぴったりの講座がたくさんあります。
様々な体験をして、新しい自分になるための一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか?
古代哲学(相対主義vs絶対主義)
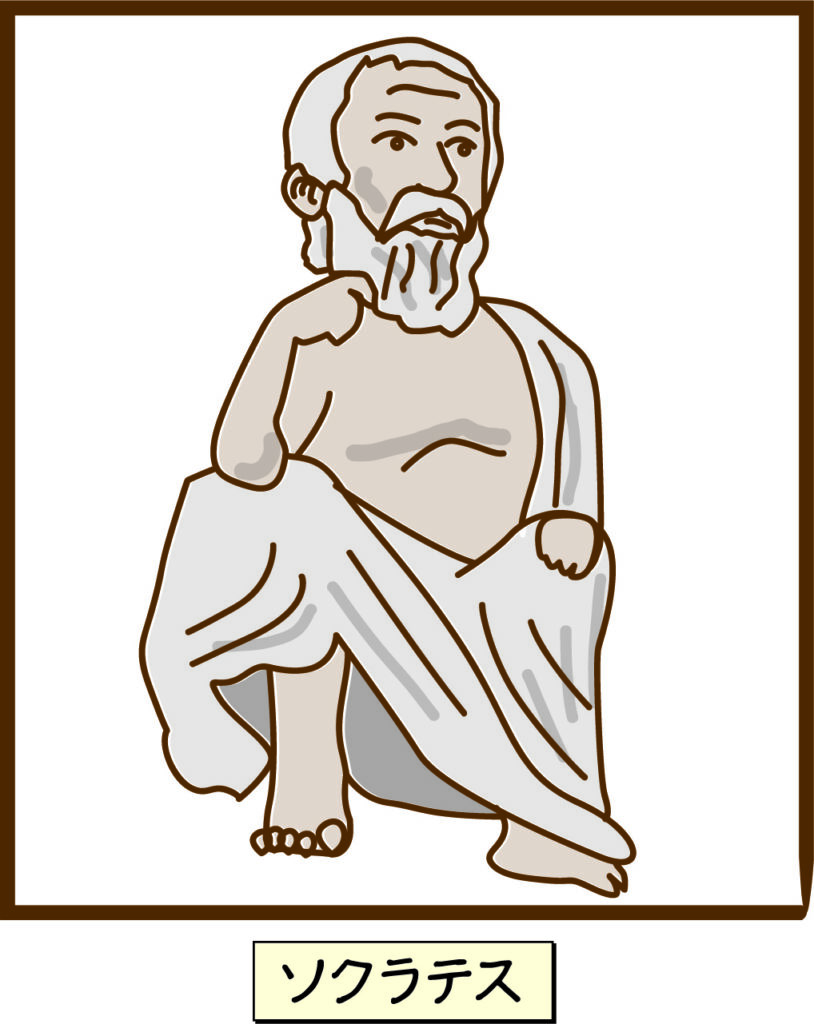
古代哲学の始まりは、およそ2500年前です。
とくにギリシアで哲学が流行しました。
その古代ギリシアで対立した二つの思想が「相対主義」と「絶対主義」です。
相対主義とは?
「相対主義」とは「物事の価値は、他との関係性によって決まるのだから、絶対的なものはない」という考え方のことです。
これは当時ソフィストと呼ばれた知者(今で言えば教師)のプロタゴラスが主張した考え方です。
例を出しましょう。
「気温15度の東京」は「暑い」でしょうか、「寒い」でしょうか。
北海道のから来た人は「暑い」と感じるが、沖縄からの人は「寒い」と感じるでしょう。
「寒いor暑い?」の一つをとってみても、「人それぞれ=相対的なもの」で、
絶対的な「暑い・寒い」を決めることはできないのです。
その他、「大きいor小さい」、「熱いor冷たい」、「善いor悪い」などの価値判断において絶対的なものはなく
それを判断する相手との相対的な関係性によって決まるのだ、というのが相対主義の思想です。
絶対主義とは?
そんな相対主義に対立するのが、「絶対主義」です。
これは「絶対的に正しい、絶対的に善い、といったものがこの世には存在するはずだ」という考え方のことです。
この主義は、かの有名なソクラテスの考え方に通じます。
ここで急ですが、皆さんに質問です。
「戦争なら人殺しは正当化されるか?」
皆さんならどう答えるでしょうか。
相対主義なら「正当化されるかは、人それぞれだ!」と考え、人殺しを正当化する人も出てくる可能性があります。
実際、ソクラテスの時代は相対主義が優勢であり、自分の意見(正しさ)をどれだけ市民に強調できるかという「弁論術」が重要視され、その意見の内容は追及されませんでした。
だから政治も少しずつですが、腐敗をしていきました。
そんな時代に生まれたソクラテスは、「人々の堕落を立て直す」という使命を抱きます。
そして彼は、相対主義とは異なる「いついかなる時も誰にとっても変わらない『善』や『正義』」を追及し、「善く生きる」ことを貫きます。
先ほどの例でいえば、「人殺しはいついかなる時も絶対に悪だ」と主張するならば絶対主義の立場ということになります。
このように絶対性を貫いた彼の行動は周りからは理解されませんでした。
そして、彼は無実の罪で投獄され、最終的には死刑に処せられてしまいました。
※この時ソクラテスは逃げることができたのですが、「自分は善く生きた結果、処刑されるのだからこの罰を受け入れる。もしここで逃げたら、それは悪であり、善く生きることに反する」と考え、みずから毒杯を飲んで死にました。
しかし、話はこれで終わりません。ソクラテスの意思を継いでみせた人物がいたのです。
それがプラトンです。
彼はソクラテスの考え方を継承し、いついかなる場合も善である、言い換えれば「善そのもの」のことを「善のイデア」とよび、
その善のイデアは我々の現実世界を超えた「イデア界」という世界にあるという画期的な考え方を提示しました。
これを「イデア論」といいます。
この後、アリストテレスという巨匠がこの考え方を否定するのですが、
とりあえず古代の哲学は以上にしておき、次は中世へいきましょう。
中世哲学(宗教の時代)

中世は古代と異なり、キリスト教が西洋の中心的な考え方になりました。
なので、哲学はどちらかというと排除されるべきものになります。
何故かというと、「神様の考えだけが正しく、それ以外の考え方は正しくない!」からです。
だから、神様の主張を補完するものとしてだけの哲学が考えられました。
とはいいつつもあくまでも哲学史的に言えば、衰退期に入りますので、今回は飛ばします。
この衰退期が終結する時代が近代です。ルネサンス(再生)です。
近代哲学(経験主義vs合理主義)

ルネサンス(再生)という言葉からも推測できると思いますが、
ルネサンス(再生)とは一度あった古代ギリシア時代の哲学を復活させよう、というものです。
神様なんかに頼らずとも、人間は人間の力で真理にたどり着けるはずだ、と考えだすようになります。
すると科学という学問が物凄い勢いで発展するようになります。
近代は科学の幕開けの時代ともいえます。
経験主義とは?
哲学に話を戻しましょう。
16世紀、まずベーコンが始めた「経験主義」が出てきます。
これは「人間が思い浮かべられる概念はすべて、経験からつくられたものである」という考え方です。
例えば「馬」という概念は、「馬」の実物や絵を実際に観察していくうちに形作られたものです。
馬を見たことない人が「馬」のことを想像することはできないと、経験主義では考えます。
しかし、「我々は「ペガサス」みたいな空想上のもの(見たことないもの)を想像できるのではないか!」と反論した人もいました。
しかし、それも経験主義によれば、人が経験できる「馬」と「羽」から形作られたものであって、あくまでも経験主義に則っていると考えます。
とにかく、経験主義はすべてを経験に委ねて考えます。
「善」という概念も同じように、小さい頃、親に喜ぶことをした経験などの積み重ねで生まれた概念に過ぎない、と考えるのです。
経験主義にとって善とは、「人それぞれの経験によってつくられた概念」ということなります。
経験主義を主張した他の大物はヒュームです。
今回は省略しますが、このように経験主義の思想は近代において大きな思想の潮流に一つになりました。
合理主義とは?
次に、「合理主義」にいきましょう。
「我思うゆえに我あり」で有名なデカルトが創始者といわれています。
「合理主義」とは「合理的に理性を働かせれば、人間は絶対的な正しさに到達できる」という考え方です。
デカルトの「われ思うゆえに我あり」の考えをまず紐解きます。
数学者でもあった彼は、数学が定理から違う定理を導き出せるように、
合理的に考えれば「善・正義」のような抽象的な概念も絶対的なものを導き出すことができると考えました。
そのために、デカルトは「絶対的な正しさ到達するには、絶対的に正しいといえる前提から出発しよう!」と考えます。
そのために利用したのが、「方法的懐疑」というものです。
これは、簡単に言えば「疑いまくれ!」というものです。
デカルトいわく「疑って、疑って、疑っても疑いきれないものは絶対正しい」。
だからあらゆるものを疑います。
まずは、経験主義がゆだねている「経験」ですが、これを否定します。
なぜなら、人は見間違いをしたり、聞き間違いをよくする、つまり錯覚を良くするから、
五感(聴覚、視覚、触覚、味覚、嗅覚)による経験はあてにならないと考えたからです。
彼はこのような形で、学問は?自分の体は?とあらゆるものを疑いました。
そして彼はいくら疑っても正しいと言えるものが一つだけ存在することに気づいたのです。
それは、どんなに疑っても、何かを疑わしいと「考えている私」だけはどんな時も存在するというものでした。
これが「我思う、ゆえに我あり」という言葉に表されているものです。
デカルトはその確実に存在する「考えている私」が合理的に導き出した結論は正しい、という「合理主義」に至りました。
このような形で、「絶対に正しいもの」を導き出したデカルトでしたが、その後の理論はあやふやになってしまい、よくわかっていません。
合理主義の立場にはその他にスピノザ、ライプニッツなどがいます。
以上のように、近代哲学は「経験主義と合理主義」の二つの思想が出てきて、
これを統合した、カントという人物もいますが、カントを書くとても長くなってしまうので、今回は省略します!
次は、現代へいきましょう。
現代哲学(実存主義と構造主義)
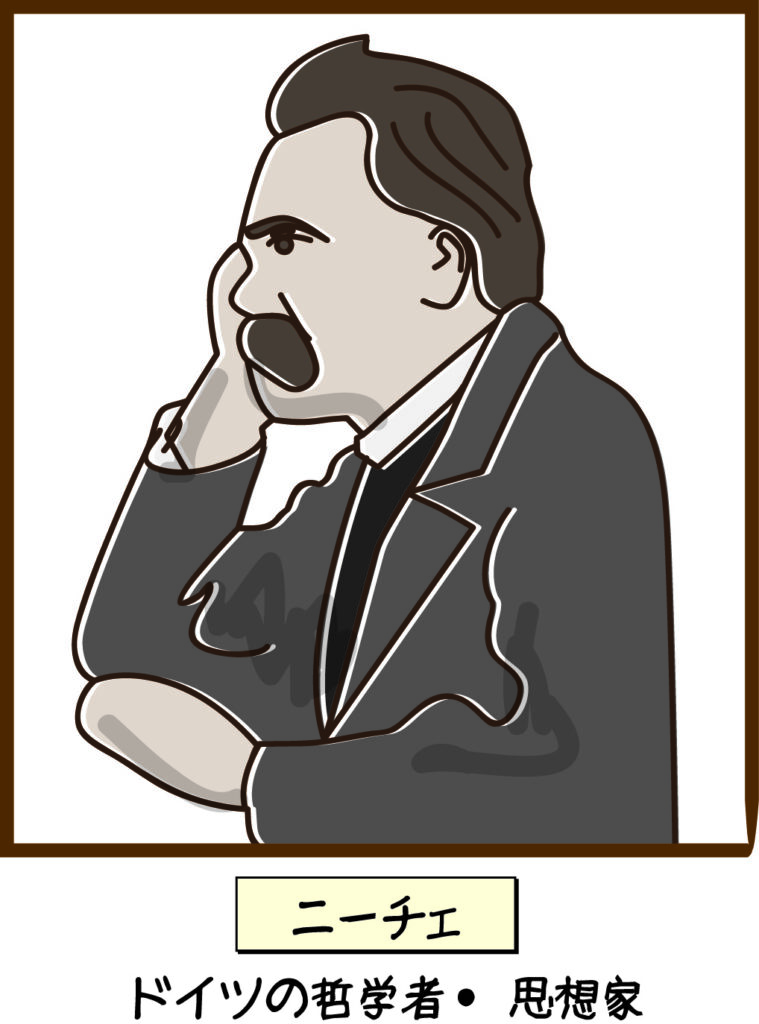
古代と近代哲学では、
- 「絶対的な善はある」という主張
- 「善とは人それぞれの(経験によって生まれる)概念だ」という主張
の二つの対立がありました。
長く続いた対立も実は現代では後者が主流になります。
最後に現代哲学について簡単に紹介しましょう。
実存主義とは?
まず19世紀に出てきた「実存主義」は、「『絶対的な善』ではなく『私という現実存在(実存)にとって善であるような真理』」を求めます。
実存主義で有名なのはニーチェです。
彼は「神は死んだ」と主張しました。
これはありもしない「神」や「道徳」を崇拝するのではなく、実存を重視して生きるべきだ、
という彼なりの主張です。
「絶対主義」も「合理主義」も人類にとっての「絶対的な善」を求めてきました。
しかし、実存主義者は
「人生は神に与えられたものでもない無意味なものであり、絶対的な善など存在しない。だからこそ、私(実存)にとっての善を探究して、主体的に生きるべきだ」
と考えたのです。主体的真理を求める点が実存主義の特徴です!!
構造主義とは?
次に構造主義です。
実存主義が個人に注目したのに対し、構造主義は「社会構造」に注目します。
「人間は主体的に生きるているように見えて、実は何らかの社会構造に支配されており、決して自由に物事を判断しているわけではない」という考え方です。
私たちは、日本で育っていること、21世紀に生まれていることなどから、無意識に自分を形作っていると構造主義では考えます。
つまり、私たちは自分で自分のことを決めているわけではなく、
あくまでも社会や時代の構造に縛られた判断をしているということになります。
逆に言えば、今となっては「人殺しは悪い」と考えているあなたも、
戦争が日常茶飯事の国家に生まれていたら、人殺しをしていたかもしれないということです。
これが構造主義の考え方ですので、ここでも「絶対的な善」は否定されます。
最後に、21世紀の哲学の主流は「ポスト構造主義」です。
「ポスト」は「〜以降」という意味です。
だから「構造主義以降」の哲学ということになります。
構造主義に反対するという思想ではありません。
そして、構造主義以降の思想という枠組みなので「ポスト構造主義はこういう思想である」と説明することはできません。
またの機会に構造主義については述べていきたいと思います。
まとめ

まとめますと、西洋哲学は近代まで大きく分けて、
- 「絶対的な善はある」
- 「善とは人それぞれの(経験によって生まれる)概念だ」
という二つの主張で対立していました。
しかし、現代哲学では前者は批判され、19世紀以降の哲学の主流は「絶対的な善」を求めるものではなくなってしまったのです。
※ただ、近年サンデルやマルクス・ガブリエルのような方々が出てきて、「絶対的な善」を求める動きもあります
えっ!?終わり?と思われたかもしれませんが、
終わりというよりも「続く」というほうが正しいのです。
哲学というものは未だ完成していない学問なのです。
そして、だからこそ今後も考え続けることができる、面白い学問なのです。
ぜひ皆さんも、哲学を学び始めてはいかがでしょうか?
ここまでご覧いただき、誠にありがとうございました。
参考文献を載せておきますので、ぜひご覧ください。
☆『正義の教室 善く生きるための哲学入門』飲茶 (著)
☆『14歳からの哲学入門: 「今」を生きるためのテキスト』 (河出文庫) 文庫 飲茶 (著)
☆『哲学と宗教全史』 出口 治明 (著)



コメント